犬の先祖
今から約6500万年前に発生した 『ミアキス』という動物が、犬をはじめとする、多くの肉食哺乳類の共通の先祖です。
ミアキスは大きさはネコくらい、顔も犬よりは猫に近く、胴長短足の体型で樹上生活をしていました。
その後、一部のミアキスが森林地帯から草原へと分布して草原生活に適した体に進化していき、約2600万年前に『トマークタス』 という動物が発生しました。
この 『トマークタス』 が、オオカミ・ジャッカル・キツネ・タヌキなどのいわゆる犬属の動物達の先祖です。
(森林に残ったミアキスは、その後さらに森林に適応して進化し、ネコ属の動物達の先祖となりました)
そして犬の直接の先祖は、オオカミとするのが最も一般的で有力な説です。
先祖とは言っても、オオカミと犬が枝分かれしたのは数万年前という地球の歴史からすれば最近のことで、生物学的にも遺伝的にもオオカミと犬は非常に近い存在です。
両者の遺伝子は99%以上の高い確率で一致していて、異種交配して生まれた子(「オオカミ犬」と呼ばれています)も繁殖能力を持つため、オオカミは犬にとって先祖というよりも、ごく近い親戚のような関係にあるとする説もあります。
※ 異種交配としては「ライガー(雄ライオン×雌トラ)」や「タイゴン(雄トラ×雌ライオン)」などの例がありますが、どちらも生まれた子には繁殖能力がなく、一代限りの交雑種です。
--------------------------------------------------------------
☆ミアキスから犬までの流れ(簡略化してあります)
約4000~6500万年前 約3000万年前 約2600万年前 約50万年前
ミアキス - クマ科動物の分化 - トマークタス オオカミの原型
(イヌ属動物の先祖)
犬の歴史
1.古代~文明の始まり
▲ 人と犬の関わり
はるか昔、人間は自然の中にできた洞窟などに住んでいました。
厳しい自然環境の中での人間は、原始的な道具や火を扱うという他 の動物にはない利点はあったものの、走るのも遅く自前の毛皮(体毛)も武器となる鋭い爪や牙も持たない、非常に弱い存在でした。
その弱さを補うために、主に血縁関係によるグループを作って集団生活をするようになりました。
しかし、人数が増えれば十分な食糧の確保が難しくなります。
その頃の人間の食糧は、自然の中の木の実の採取や集団での狩猟などによって得ており、一つの地域での収穫量が少なくなると別の地域に移動する生活を送っていたようです。
そして人間が生活するすぐそばにも様々な動物達が存在していて、その中に現在の犬の祖先となる動物もいました。
最初はまったく別々の生活圏を持っていたイヌと人間ですが、徐々にイヌは人間の生活域から出る残飯(動物の骨や皮など) によって安定した食物を得ることを覚え、人間のすぐ近くで生活するようになりました。
原始的な生活をしていた人間にとっても、残飯の処理をしてくれるイヌの存在は住環境を衛生的に保つために重宝で、その上見慣れないものに警戒して発するイヌの吠え声は、弱い存在だった人間に危険な肉食獣などの外敵の接近(特に夜間) などを知らせることにもなり、いわば『ギブ・アンド・テイク』 の関係が成り立つようになりました。
そして人間の近くで暮らすようになったイヌは、狩りの獲物が少ないなどの食糧難の時には、貴重な蛋白源にもなったようで、貝塚などの遺跡からは、食犬の痕跡と思われる、人間の歯型のついたイヌの骨も発見されています。
▲ 犬が飼われるようになったわけ
イヌと人間が接近して、生活空間が重なり合うようになったのが大体4~5万年ほど前、そして人間がイヌを意図的に飼育するようになったのは、1万2千年くらい前だとされています。
しかし、2~4万年くらい前の遺跡から、人間がイヌを飼っていたと思われる痕跡も見つかっていて、はっきりとはわかっていません。
その頃すでに出来あがっていた人とイヌとの『ギブ・アンド・テイク』 の関係を発展させ、まだ小さな仔イヌを捕らえるなどしたところ、仔イヌがよく人になれたことがきっかけになったようです。
ごく初期には、イヌの役割は番犬や食用としてのものだけでしたが、簡単な命令や号令に従うことがわかってからは、狩りにもイヌを連れて行くようになりました。
優れた嗅覚と聴覚を持つイヌは、人間よりも早く獲物を発見して追い込んだり、しとめるなどして大きな助けとなったことから、積極的にイヌを飼育するようになったようです。
イヌにはもともと 『群れ本能』 というものがあます。
孤独を嫌い群れと共に行動し、自分よりも強いものや群れのリーダーに絶対服従するというイヌの持つ習性が、イヌの飼育を始める上で大きな助けになったと考えられています。
▲ 犬が人にもたらしたもの - 牧畜のはじまり -
人がイヌを飼い馴らすという行為は、想像以上に人間に大きなものをもたらしました。
それは 『野生動物の中には飼い馴らすことができるものがいる』という発見です。
何でもないことのようですが、この発見によって『牧畜』 が発明され、人間の生活が根底から変化・発展することになりました。
イヌを飼い馴らした要領で、それまでただ狩りをしてその場で食糧にしていた草食獣の中から、幼いものや気質の大人しいものを選んで馴らし、いわば食糧を備蓄することができるようになったわけです。
この時もイヌは人にとって大きな助けになりました。
馴らされた草食獣も群れの一員と認識したイヌは、家畜となったこれらの動物が逃走するのを阻止し、貴重な家畜が外敵に襲われるのを防ぐという役割も担うようになりました。
イヌの協力を得た人間は、牧畜の規模を拡大し、それまでの不安定な移動生活から定住生活を送れるようになり、やがて農耕を行うようになり、住居や装飾的な道具の作成などの『文化』 を発展させていきました。
▲ 番犬から軍用犬へ
それまでの人間にとって、最も有用なイヌの能力は『番犬』 としてのものでした。
人間が定住生活を送るようになって食糧などを蓄え、次第に大きな集落を形成するようになると、人間は肉食獣だけでなく同じ人間をも強く警戒する必要が出てきました。
時に食糧やより収穫の多い土地を得ることを目的として、また時には自分たちの勢力をより大きなものとするために、集落同士の争い(戦争) が起こるようになったからです。
そのため、動物だけではなく見慣れない人間にも警戒して吠える、番犬の役目は非常に重要視されました。
異変に気付いて吠えたてる犬の声によって、侵入者を迎え撃つ準備をすることもできたでしょうし、もしも盗みが目的の侵入者ならば、犬に吠えられるのを嫌って、その集落を襲うのは諦めたことでしょう。
その後、集落がさらに大きくなって小国家と呼べるような規模になってくると、次第に国家間の戦争が起こるようになりました。
戦争といっても、この頃の武器は剣や弓矢などが主で、現在のような銃や大砲、ミサイルのような飛び道具はほとんど存在せず、人間同士のぶつかりあいの、いわゆる白兵戦でした。
そして、それまでは番犬として浸入してくる外敵を追い払うのが目的だったイヌの警戒心や攻撃性が、「武器」として利用されるようになりました。
古代エジプトやローマの都市国家などでは、特に大型で攻撃性の強いイヌを選んで(マスティフ系など)、釘を植え込んだ首輪や鎧のようなものをつけて、敵の真っ只中を走り回らせるという戦法を行い、大きな戦果をあげていたようです。
強力な武器である優秀な 『軍用犬』 を多くもっていた小国家は、近隣との勢力争いで優位にたち、徐々に勢力範囲を広げて、やがて統一国家を作るまでになっていきました。
2.紀元前~中世
▲ 犬種のはじまり
最初は野生のイヌを飼い馴らし、生まれた仔犬の中から望む性質を持ったものだけを残すという方法をとっていた人間ですが、徐々にイヌの個別の性格や性質の違いを比較して、より飼いやすい、より人間の役に立ってくれるイヌを求めて、イヌの交配にかかわるようになりました。
初期 (原始時代) のイヌを飼い始めた頃の人間が重要視したのは、優秀な番犬となるために必要な、異変に敏感に反応してよく吠える性質で、後に牧畜を行うようになってからは人間に馴れやすいイヌや、従順で熱心に作業を行うといった性質も重要視されるようになりました。
自分の望む資質を持った犬同士を選んで交配し、産まれた仔犬の中から優秀な性質を持つ仔犬を選んで残すという方法で、新たな犬種を作り出していきました。
その後人間の生活がある程度安定し、国が生まれ文明が発展し、人間に職業というものがうまれてくると、イヌの役割も飼い主の職業に応じて専門化・細分化が進みました。
王や裕福な者は、自分の身や財産を守ってくれる優秀な番犬を求め、牧畜を専門に行う者は、不審者や外敵に対して強く反応する縄張り意識の強さや家畜を追って走り回るスタミナと確実に自分の指示に従う従順さを持ったイヌを求め、狩猟を行う者は、獲物を確実に発見してくれる優れた嗅覚や獲物を前にして尻込みすることのないガッツを持ったイヌを求めるようになったわけで、それぞれ自分達の望む性質を持ったイヌを選んで積極的に交配に関わるようになりました。
このことによってただ単にイヌとひとまとめにされていたイヌが、その役割によって『番犬』 『牧畜犬』 『猟犬』 と大きく分化され、現在まで続いています。
▲ 牧畜の発展
自分達の希望にかなうイヌを求めてイヌの選択交配を進め、『牧畜犬』や 『猟犬』 を生み出した人間は、結果として初歩の遺伝学を発生させたことになり、『家畜の品種改良』が可能であることを知りました。
たとえば他の牛よりも乳の量の多い牛を選んで交配させて『乳牛』 を作りだし、より肉付きが良い牛を選んで『食肉牛』 を作り出しました。
家畜の品種改良を行うようになって牧畜の生産性は向上し、人間の食糧事情もより向上し、さらに大きな国家も作られるようになりました。
3.中世~近代
▲ 銃と犬の関係
人間が銃を発明すると、それまでの狩猟方法は一変しました。
銃が発明されるまでは、狩りをする時には弓矢などを使っていて、ある程度獲物の近くまで近寄る必要がありましたが、銃によって人間は獲物に近寄ることなく狩りを行うことができるようになり、同時にイヌにも新たな要求が向けられました。
主人のそばを離れて撃ち落とされた獲物を探し当て、食べてしまうことなく人間の元へ運んでくるということは、犬により強い服従心を求めることになり、更なる犬種改良が進められました。
その他にも獲物となる動物の違いによって、狩猟スタイルも多様化していき、犬に求められる能力も多様化していきました。
鴨などの水鳥猟をする時には、水の中に落ちた獲物を回収するために泳ぎが上手であったり、体温の低下を防ぐために毛の量が多いとか長毛であることが有利になります。
ウサギなどの穴に隠れた獲物を探すためにはより鋭敏な嗅覚や、時には巣穴に潜り込んで獲物を追いたてるために小回りのきく小さな体が求められます。
その他、繁みに隠れたウズラやキジなどの野鳥を獲物とする場合には、隠れた獲物を探し当て、繁みから追いたてるために、バネのように飛びかかって鳥を飛び立たせたり、逆に逃げられてしまわないように、音をたてないように身動きもしないでじっと主人に合図を送る、特別な能力が求められるようになりました。
その結果、一口に 『猟犬』 と言っても、獲物となる動物ごとに『ガン・ドッグ(鳥猟犬)』、『ハウンド(獣猟犬)』、『テリア(ネズミなどの小害獣用の猟犬)』の3つに大別されるようになりました。
▲ 貴族による犬の育成
人間の貧富の差が拡大し、王族や貴族が誕生すると、犬も新たな発展期を迎えることになりました。
税収という収入源を得た王族や貴族達は、直接労働をする必要がなくなり、時間的なゆとりが出来ました。
同時に食糧を得る手段として行われていた狩猟も、彼らにとってはスポーツや社交という新たな面を持つようになり、実用的な能力が重視されていたイヌにも、装飾性や愛玩性というものを要求するようになりました。
役に立つだけではなく、外見も自分の好みにあうイヌを求めるようになったわけです(時間的・気分的なゆとりが生まれたせいですかね)。
この要求を満たすために、それまでの選択交配に加えて、突然変異も多く活用されました。
例えば美しい長毛を持っていたり、真っ白なイヌや極端に体の小さなイヌが珍重されたりしたこともあり、突然変異によって生まれたこのような特徴を固定させようと、いろいろな試みがなされました。
イヌの小型化が進んだのもこの頃で、貴婦人達が抱いたり可愛がったりするための『愛玩犬』 が誕生しました。
その良い例がプードルで、もともと体も大きく鴨猟などに使われていたものが、水中で行動しやすいように独特の被毛の刈り込みを行ったところ、そのスタイルがフランス宮廷の貴婦人達の間で人気となり、より可愛がりやすい小型化への希望によってミニチュア、トイと小型のプードルを誕生させることになりました。
▲ 犬、海を渡る
現在、犬は赤道付近の亜熱帯に近い温帯地域から永久凍土の存在するシベリア平原のような寒帯地域、山岳部から草原まで、世界の広い地域にわたって分布しています。
氷河時代の終わりのまだ海が浅かった頃に、地球上のあらゆる地域へ移動・分布した人間がイヌを伴った結果のようです。
氷河期が完全に終わって各大陸が隔てられると、イヌの体も被毛の長短や体格の大小など、その土地の気候風土に合わせて変化していき、それぞれの土地で地犬(じいぬ)と呼ばれる土着のイヌとなりました。
15世紀頃、ヨーロッパ諸国が新たな植民地や冒険を求めて海を越えるようになり、大航海時代と呼ばれる時代に入ると、海に隔てられていた大陸が発見され、同時にその土地に適応した地犬達が発見されました。
時に香辛料や珍しい食物などと共に、これらの犬もヨーロッパに持ちかえられて珍重されていたようです。
ヨーロッパからも、17世紀になってイギリスから新天地を求める一団が船で新大陸アメリカを目指した時には、2頭の犬を連れていたという記録があり、アメリカ開拓が始まってからは、猟や牧畜の手助けの他、家庭犬として人々の心の慰めにもなったようです。
その後、新たな移民がアメリカを目指す度に人々は犬を連れて行ったようで、それらの犬がアメリカン・コッカー・スパニエルなどのアメリカ原産の犬達の先祖となりました。
またオーストラリアへの移民が行われるようになってからも、犬は人間と一緒に新天地に移り住み、広大な土地での牧畜に力を発揮しました。
このように人間が移民や戦争などの理由で犬を伴って長距離を移動するようになったことで、地方ごとの土着の犬種の発見や、連れて行った犬と土着の犬との交配などによって、また新たな犬種が生み出されました
4.近代~現在
▲ 犬種の確立 -ドッグショーの始まり-
19世紀に入る頃には様々な犬種が生み出されていましたが、同じ犬種であっても、個体ごとの能力や容姿にはまだまだ差やバラつきが多くありました。
それまでは新犬種の作出や育成は貴族などが個人で行っていましたが、個人で多数の犬を飼育しその能力を維持するための育成を行うには限界があり、自分の作り出した犬を多くの人々に公表して飼育を促し、個々の犬種をより磨きあげようという動きが出てきました。
(民主化が進んだことで貴族の没落や庶民が財力を持つようになったことも一助となったようです)。
そのため、自分の犬を発表する場として1859年に、イギリスで最初のドッグ・ショーが開かれました。
最初のドッグ・ショーはセターとポインターの2種のみで行われましたが、その後ショーが盛んに開催されるようになるにつれて、出場する犬種も徐々に増えていきました。
ドッグショーが開催されるようになると審査の基準が必要になり、個々の犬種の理想とされる姿を細かくまとめた、『犬種スタンダード』というものが編纂されました。
(犬の体格や骨格のありかた、歯の噛み合わせや被毛の色合い、気質まで、あるべき姿が詳しく決められています)
『スタンダード』 によって犬種が確立され、ひんぱんにドッグショーが行われるようになったことで、犬のブリーダーには、大きな目標ができました。
そして、 『スタンダード』 が犬種を育成する指針となりました。
▲ 犬の能力の再発見と再認識
長い間、牧畜や狩猟など主に労働面で人間の助けとなっていた犬ですが、近代に入って『家庭犬』 としてより人間と密着した生活を送るようになり、犬の持つ能力や服従心、忠誠心が再発見・再認識されるようになりました。
例えば、目の不自由な主人を気遣う犬がいたことから『盲導犬』 という発想が生まれ、組織的に盲導犬が育成されるようになり、その後『聴導犬』 や 『介助犬』 といった様々なサービス・ドッグが生み出されました。
このようなサービス・ドッグが一般に広まっていく中で、犬の人間に対する愛情や忠誠心が高く評価されるようになりました。
また、科学の発達によって犬の嗅覚や聴覚がどのくらい優れているのか、具体的な数字として表されるようになり、犬の能力に対する信頼と期待はますます高まっています。
現在では 『てんかん発作予知犬』(てんかんの発作が起こる前に分泌される、ごくごく微量のアドレナリンなどの臭いを感知して、パートナーに発作が起こりそうなことを知らせます)や、『皮膚ガン感知犬』(ごく初期の皮膚ガンの細胞が発する臭気を感知して、ガンの発生部位を知らせます)といった特殊な役割を持つ犬を育成する動きも始まっています。
▲ パートナーとしての犬
20世紀に入ってペットとして動物を飼う人々が増えてくると、動物が人間に与える『癒し』 の効果が注目されるようになりました。
特に身体に障害を持つ人達が盲導犬や聴導犬といったアシスタント・ドッグを身近に置くことで、単に不便さが解消されただけでなく、日々の生活にハリが出て積極的に行動できるようになったという精神的な効果が報告され始めました。
1970年代には、アメリカで農場滞在型の体験スクールを開催していた『グリーン・チムニーズ』 が、虐待を受けた子供達の精神的なケアを行うために、積極的に子供達に動物との触れ合いを持たせることで、従来のカウンセリングなどで癒しきれなかった心の傷を癒し、更正や自立を促す成果をあげ始め、人と動物が共に生活することで生まれる精神的・肉体的な関わりに強い関心が向けられるようになりました。
このような効果を研究するために、1970年代後半にアメリカでデルタ協会が創立され、獣医師や心理学者達が協力して、『人と動物との絆(ヒューマン・アニマル・ボンド=HAB)』の研究をスタートさせました。
現在ではHABの研究がすすみ、医療現場でも『動物介在活動(AAA)』 や 『動物介在療法(AAT)』といった活動が積極的に行われるようになり、身体的に障害のある人や精神的に障害のある人、長期療養患者やホスピスケアを受けている患者、独居者やお年寄りの心を癒す効果が、高く評価されています。
このような活動の場でも犬は大活躍していて、最近では『セラピー犬』 という言葉も徐々に定着してきました。
▲ 新しい犬種に賭ける夢
現在でも、新しい犬種を生みだす試みは行われています。
例えばラブラドールとプードル、コッカー・スパニエルとプードルをかけあわせて新しい犬種を作ろうとしている国もあります。
この試みは興味本位のものではなく、犬の毛に対するアレルギーを持っているために、盲導犬や聴導犬をパートナーとすることを諦めざるをえない視覚障害者や聴覚障害者のニーズに応えようという真摯な心から始まりました。
(プードルは人との絆を強く求めるというアシスタント・ドッグとして欠かせない性質に加えて、毛が抜け落ちないという特徴を持っています)
もちろんこれらの新犬種を作り出すための交雑は、専門家による緻密な計画の元に慎重に行われていますし、犬種として確立するまでにはいろいろなハードルをクリアしなくてはならず、長い時間が必要になります。
20年ほど前から始まったこのような試みは、まだまだ試行錯誤を続けている状態ですが、徐々に成果をあげていて、新しい『アシスタント・ドッグ』 として高い期待をかけられています。
犬という生き物
まずは飼い主
ペット飼育と集合住宅にまつわる問題に直面したこと・・・。
飼い主さんが高い意識を持たないと、特に動物が密集している地域では大きな問題になるのだということを実感しました。
そこで、飼い主さんに認識してもらいたいこと。
まず
・しつけは犬を飼育する以上絶対に不可欠である ということ
大型犬じゃないからしつけがいらない、小型犬だから飛びついても吠えてもいいというわけではありません。
むしろ大型犬の飼い主さんのほうが意識が高く、小型犬の飼い主さんのほうが 吠えようがあちこちにオシッコをしようが人を噛もうが気にしないということが多いような気がします。
教えなければ犬は勝手に犬らしい行動を起こします。
あちこちにオシッコをしたり、吠えたり、物を壊したりするのは犬としては当たり前です。
子犬のうちは遊びのつもりで甘噛みもしてくるでしょう。
ちゃんと教えてあげないといつまでたっても犬は犬のままで、人間社会で一緒に暮らす上で困った存在になりかねません。
犬という生き物を理解して、きちんと人の中で暮らすためのルールやマナーを教えていかないといけません。
しかし逆に犬を理解しているつもりで多いのが「これは個性だから」と犬の困った行動を何の問題もないことだと思ってしまうこと。
というわけでもうひとつ認識して欲しいのが
・問題行動は「犬の個性」ではない ということ
これまでも書いてきていますが吠えやすい犬や落ち着きのない犬、興奮しやすい犬はいます。
それは犬種特性であり、気質は個性とも言えるかもしれません。
それぞれの家庭の環境にあった犬を選ぶのが、問題行動を減らす第一段階とも言えるでしょう。
でも、その子たちが実際に吠えまくったり公共のものを壊したり、人を噛んだりするのも「この子はしょうがないのよ、ワガママだから」と楽観していては犬嫌いを増やすもと。
個性に合わせた対処をして、問題行動を起こさないよう飼い主さんがきちんと努力をするべきなんです。
犬らしい行動をゼロにすることは不可能です。でも、人に迷惑をかけないように飼い主さんが気をつけ管理することは可能なはず。
自分にとっては気にならないことでも、他の人から見たら犬嫌いの人から見たらどうなのかを考えるべきではないかと思います。
特に、ペット可マンションなど動物たちが密集する中では犬を飼っている人も、犬が苦手な人もお互いがストレスなく暮らすためにきちんとしたルールやマナーをそれぞれが守る必要があると思います。
ペット可の意味
最近はペット同伴でいろいろなところに行けるようになりました。
ドッグカフェやペット可の宿泊施設や観光施設も増えていますよね。
動物病院やトリミングサロンもそうですが、こういった公共の場にわんちゃんを連れて行くのであれば、しつけをしっかりし、飼い主さんがマナーをしっかり守らないといけないと思います。
勘違いしてはいけないと思うのですが「ペット可」=「あれこれやらかしても許される」ではありません。
ペット可マンションだから吠えても大丈夫と無駄吠えを放置している方も多いですしお店で排泄させほうだいだったり、最低限のマナーすら守らない人も。
「ペット可マンションなんだから、吠えても当たり前でしょ?」
「ペット可のお店なんだから、お店の人が片付けてくれるんでしょ?」
という甘えは通用しません。
特に吠えや排泄の問題はマナー意識をしっかりもっていただかないと、特にペット可マンションなどでは大きな問題になっています。
「うちでも飼ってるから苦情を言いにくくて・・・」といいたいことを飲み込んでしまい、ある日突然不満が爆発!ということも多いんですよ。
苦情がきていない=問題ない というわけではないんですね。
ちょっとの吠え声にビクビクする必要はないと思いますが、吠え続けるのは迷惑になりますので制御する方法を飼い主さんが学ぶべきだと思いますし、たくさんの人が出入りするところでは、マナー意識をより高くもつこと不可欠だと思います。
自分が気にならないからといって、他人がそうであると思ってはいけないと思います。
吠える声も毛も臭いも犬好きにはかわいいものですが、そうでない人にとっては非常に気になるものだったりするんです。
マナー違反の飼い主さんやしつけ不足わんちゃんのせいで、犬と暮らせる物件が減ったり、「これだから愛犬家は」といわれないように一人一人がしっかり意識を持っていただければと思います。
一番大切なこと
しつけをしていく上で、一番大切なのは飼い主さんとの信頼関係だと思います。
普段から「人の言うことは聞くものだ」という意識のない子だとコミュニケーションをとるのはとっても難しいのです。
そういう子の「吠え癖を治してください」「引っ張り癖、飛びつき癖を治してください」
とひとつの困った行動だけをどうにかしようとしてもなかなか難しいんです。
普段から「飼い主の言うことには耳を傾けるものだ」という認識のない子に、「コレだけはするな!」というのはほとんどムリなので、結局のところひとつの問題行動の解決のためにはこれまでしてきた犬への接し方全般を見直してもらうことになります(接し方がまずい場合、飼い主さんが認識してないだけで問題行動はあちこちにあるのが普通ですが)。
愛情をあたえてるつもりでも甘やかしてばかりでは犬になめられるだけで、飼い主さんのいうことをちゃんと聞こうという気にはなりません。
この人のいうことを聞くといいことがあるな、褒めてもらえてうれしいな
ママ大好きだな、と思われるのが理想です。
よく何か犬が問題を起こすと「上下関係が」「自分をリーダーだと思っているから」「アルファー症候群ですね」とすぐに犬と人の関係を狼の群れの関係と混同している意見をいろんなところでみますが
犬は人を犬だとは思いませんし、自分を人だと思うこともありません。
家族というグループの一員だとは認識するでしょうが、自分がボスだから噛むのではないんです。
「犬は常にリーダーを取って代わろうとしている」というようなこれまでの「優位性」の考え方は行動学会では覆されています。
飼い主は犬に対してどうなるべきか?といえばリーダーではなく優しい保護者であって欲しいと思います。
そして、人間社会のことをやさしく教えてあげる先生であってほしいと思います。
犬にとって分かりやすい言葉を使って、失敗しないように導いてあげればわんちゃんたちは飼い主さんのことが大好きになるでしょう。
ただ、甘やかすのではなく、その子のことを考えてしっかり教育をしてあげること
それがすごく大切なんだと思います。
しつけは楽しみましょう
別に犬を飼っている人全員が号令をばっちりマスターして犬との関係に緊張感を持って、「アレやっちゃダメ、コレやっちゃダメ!」と厳しく監視しろといってるわけではありません。
わんちゃんが他人に迷惑をかけず、家庭の中で問題なく暮らしていればそれ以上のことは特に必要ないし、あとは飼い主さんの好み次第だと思ってます。
なーんにも教えなくても、吠えないしトイレは失敗しないし、とびつかないし、人は大好きだしというトレーニングいらずの優等生も実際にいますからね。
もちろんトレーニング(とくに子犬のうちの基礎トレーニング)はしたほうが、問題行動の予防にもなるので、どんな子でもお勉強はしたほうが絶対にいいです。
一応お勉強として、個人的に競技会に向けて日夜努力する!とか、発表会にむかってドッグダンスを練習したりとかそういうところまではしてないです。そのあたりのレベルになると趣味の問題だと思うので、やりたい人はやればいいレベルだと思います。
でも遊ぶときやご飯を食べるとき、ケージの出し入れなど日常なちょっとしたことにしつけを組み入れて、号令を使ってべにとコミュニケーションをとってはいます。
ちょっと難しいタイプの子やとっても元気なタイプの子とめぐり合った方はぜひトレーニングをがんばってみて欲しいと思います。やってみるとやりがいがあって楽しいですよ。
大切なのは楽しむことだと思います。
別にお仕事をするわけではないので、しつけに一生懸命になりすぎて厳しくやりすぎてわんちゃんとの日常が緊張感の連続になってしまっては、本末転倒です。
家庭犬なんですもの。ゆっくりまったりで十分です。
しつけしなきゃ!とガチガチになってしまって、お互いリラックスできなかったら楽しみも半減。
それだからこそ、子犬のうちから問題行動の予防に努めていただきたいと思います。
そのほうが出てきた問題に対処するより100倍楽なんです。
あせらずのんびりしつけを楽しむと、わんちゃんとより深くコミュニケーションが取れると思いますよ。
しつけの重要ポイント(1)
犬の扱いがうまい人とそうでない人は何が違うかといえば
ひとつは
声のトーンのメリハリ
特に女性に多いのが、コマンドもおしゃべりも褒めるのも叱るのも全部おんなじ高めのトーン。
大騒ぎしている子に高い声で「こら~何やってるの~?」 「やめなさいっていってるでしょ~!!」
といってはより興奮させてしまいます。
逆に男性では褒めるときも「無言(なでなで)」とか「よしよし」ボソボソと暗くてあんまり褒められた気になれない ということが多いですね。
犬とのトレーニングは結局のところ異文化コミュニケーションなので
伝わらなければ意味がない!←ここ重要。
叱ってるつもりでも犬が喜んでしまっていれば褒めているのと一緒なんです。
逆に
褒めてるつもりでも、犬が喜んでいなければ褒めていることになりませんし、
「号令」のつもりでも、伝わらなければただの「独り言」
「おりこう」「よしよし」と言いさえすれば、褒めていると思っていたり、なでること=褒めることであると思っている人がいますが、そうではありません。
「おすわり!!」「ふせ!!」と号令を連呼すれば伝わると思っている人も多いですが、そうではありません。
ちゃんと犬にこちらの意図が伝わるように、声のトーンを使い分ける必要があるんです。
また、よくテレビなんかで褒めるときは「よしよしよし!!」と高い声でわしゃわしゃとムツゴロウさんのように犬をなで繰り回すようすすめられたりしていますが、わしゃわしゃ触られるのが好きな子はいいでしょうが、興奮しやすい子にこういうトーンでそんななで方をするとさらに興奮を煽ってしまいます。噛み癖が治っていない子犬なら、興奮してその手を噛むでしょう。
他にもいろいろ要因はありますが、トーンだけで言うのであれば、興奮を落ち着かせたいなら、ゆっくりおだやか低めのトーン。
逆にちょっと怖がっている子やテンションの低い子にやる気を出させたいときは高めではっきりしたトーンで話しかけてあげる必要があります。
犬のテンションを見極めて、号令などのトーンを変えると、うまくいきやすいんです。
とはいっても、自分がどんなクセをもっているのか、指摘されないと分からないこともたくさんあります。
わんちゃんと飼い主さん両方のクセを見て、合うやり方を教えてもらうことができるのでしつけは実際に教室で教えてもらうのが一番ですね。
しつけの重要ポイント(2)
続きになりますがちゃんといいことができたときのごほうびを何にするのかということもとても大切なポイントになります。
麻薬探査犬などお仕事をしている子たちは、なでてもらったり大好きなおもちゃで遊んでもらうことが一番のごほうびになっているようです。
あの子達は、普段はケージの中にいて、外に出るのはお仕事のときのみ、お仕事がゲームの一環になっている、というような生活をしています。
ですから、短い時間でもハンドラーとのコミュニケーションが楽しくてしょうがないんでしょうね。
普段なでられていない子は、なでられることや、声をかけてもらうこと、おもちゃを借りることが本当にうれしいすばらしいごほうびになります。
人で言うと軍人さんや全寮制の学生たちのような生活でしょうか?
一般人(家庭犬)とは全然違う生活ですよね。
わたしが対象にしている子は家庭犬ばかりなので普段からなでられまくって、声をかけられまくっているのでどちらも大喜びするようなごほうびにはなりにくいです。
そんなわけで、手っ取り早いごほうびは「おやつ」になります。
わんちゃんのサイズにもよりますが、子犬なら小指の爪の先くらいの大きさまで小さくちぎった
おさんぽ君やマイルドチップ、ドライレバーなどを使います。
「おやつ」をつかってトレーニングをすることで、「これがいいことなんだよ」と手っ取り早く教えることができますし、いい行動を普段の生活に取り入れることも楽にできるようになります。
あくまでこの「おやつ」はこれがいいことなんだよ!と教えるきっかけであり、ずーっと使い続けなければいけないものではありません。
おやつだけでなく、大好きなおもちゃがあればそれをごほうびに使えばいいですしどれが一番のごほうびになるのかは、わんちゃんとお付き合いしている飼い主さんでないと分かりません。
しっかり観察して、どれが大好きなのかを見極めてあげてくださいね。
そして、わんちゃんが大好きなものは、ごほうびになるように出し惜しみしてあげっぱなしにしておかないことが大切ですね。
どんな美味しいごちそうでも、すてきなものでも常にそこにあり続ければ価値はなくなってしまいます。
上手にごほうびの価値をあげておく必要があります。
また、簡単なことを教えるのにも常に最高のごほうびを使っていると、価値がなくなっていくのでごほうび大好きランキングを作って、難易度ごとにごほうびのランクを変えるとより効果的になります。
おうちの中ではドライフードで練習していても、外の刺激のある環境ならドライレバー、などというふうに差をつけるようにして、やる気をださせるとすごく効果的なんです。
「おうちだとできるけど、外だとできないんです」という方、ごほうびの使い分けをしてみてはいかがでしょうか?
外の刺激に勝てるほどのいいごほうびがあれば、やる気もぐんとあがりますよ。
もちろん、刺激が強い分だけ、おうちのなかでやるより簡単にしてあげないといけませんけどね。
犬の年齢
1.犬と人間の年齢比較
※個体差や犬種によって違いがあります※
犬 人 犬の身体や心の変化
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3週 1歳 音に反応するようになり、目も開く。 乳歯がはえ始める。
兄弟犬とじゃれ合うことにより、犬同士のつきあい方を覚える。
基本的な性格が現われてくる。
6週 2歳 乳歯がはえそろう。 離乳開始。
2ヶ月 3歳 親離れの時期。
新しい環境や他の動物 (人間を含む) への適応ができるようになるため、飼い始めるのはこの頃 (2ヶ月~3ヶ月になるくらいまで) が最適。
母犬から貰いうけた免疫がなくなり始めるので、第1回目のワクチン接種を行う。
3ヶ月 5歳 永久歯がはえ始める。
第2回目のワクチン接種を行う。(外への散歩はワクチン接種が済んでから)
狂犬病の予防接種を受け、市町村の保健所への登録が必要になります。
6ヶ月 9歳 永久歯がはえそろう。
家族の中での上下関係と自分の地位の確認行動 (順位付け) が見られるようになる。
本格的なしつけを始める。
10ヶ月 15歳 メスは、この頃に最初の発情を迎える。
オスは、肢をあげてオシッコをするようになる。
1才 18歳 ほぼ成犬となる。(大型犬や超大型犬は、まだ成長途中です)
2才 22歳 大型犬や超大型犬でも体の成長が完成する。
3才 26歳 やんちゃだったり騒々しい性格のコでも、落ち着きが見えてきます。
4才 30歳 U^ェ^U
5才 34歳 5才を過ぎての初産は、妊娠中毒症などが出やすくなるので、注意が必要です。
6才 38歳 寒さに対する抵抗力が弱くなってきます。
外飼いの場合、夜間だけでも玄関などの風の当たらない場所に入れてあげると良いでしょう。
7才 42歳 毛色の濃い犬では、白髪が見られるなど、老化の兆しが現れてきます。
高齢になってからの肥満は危険! 運動量が減ってきたら老犬用のフードに切り替えましょう。
8才 46歳 U^ェ^U
9才 50歳 散歩は犬の体力にあわせて、無理をさせない範囲で行ってください。
10才 54歳 病気に対する抵抗力も弱くなります。
健康診断は定期的に。
11才 58歳 気温の激変で体調を崩しがちです。
季節の変わり目には注意してあげてください。
12才 62歳 暗い所を恐がるようになったら、視力が衰えてきている証拠。
夜、暗くなってからの散歩はやめましょう。
13才 66歳 名前を呼んでも反応しない場合、聴力の衰えが考えられます。
14才 70歳 最近では、痴呆症になる犬もいます。
食餌をさせたばかりなのに催促をするようになったり、1ヶ所でグルグル回るような行動が見られるようになったら、注意が必要です。
15才 74歳 足腰が弱くなり、小さな段差につまづいたりするようになります。
※一般的に、大型犬よりも小型犬の方が成長は早く、老化は遅く進む傾向にあります。
犬は人間よりもずっと早いスピードで成長します。
特に仔犬の時期は、1ヶ月が人間にとっての1~2年に相当しますので、「まだまだ仔犬だから…」と思っているうちにぐんぐん体も大きくなり、あっという間に成犬になります。
2.仔犬時代
▲ 社会化期
生後2~3ヶ月頃は、仔犬の 『社会化期』 と呼ばれ、社会性を養う大切な時期です。
それまで動き回ることも少なく、母犬のお乳を飲んでは眠るだけだった生活から、自分の肢で歩き回るようになり、兄弟犬や母犬とのじゃれ合いを通じて、犬としての行動の基本ルールを学んでいきます。
まず強く噛んだことを兄弟犬や母犬から叱られることで、力加減をすることを覚えます。
そして、兄弟ゲンカの中で、負けを認めたら服従の姿勢を取ってそれ以上の争いを避けることを覚え、同時に服従姿勢を取った相手を攻撃してはいけないことを覚えます。
その後、社会化期の後半に入ってからは、兄弟犬や母犬以外の犬と触れ合うことで、初対面の相手とどのように接すればいいのかを学んでいきます。
性成熟を迎える前の仔犬には仔犬特有のニオイがあり、このニオイには成犬の攻撃的な気分を抑える効果があります。
そのため、仔犬は犬同士のルールを破ったりマナー違反をしたとしても、多少は大目に見てもらえます。
たとえハメを外し過ぎて叱られるような場面でも、鼻先で小突き回されたり、抑えつけられたりする程度。
どんなに厳しく叱られても歯を剥いて威嚇されるくらいで、ケガをするほど強く噛まれることはありません。
成長するにつれて仔犬臭は薄れていき、徐々に強く叱られるようになりますが、大目に見てもらえる時期があることで、ケガをすることなく、自然に犬同士の付き合い方を覚えることができます。
(上下関係の厳しい犬社会では、成犬が仔犬と同じようなルール違反をした場合、厳しい攻撃を受けることになります)
健全な社会化期を過ごして十分な社会性を身につけられるかどうかは、その仔犬のその後の一生を左右するほど重要な意味を持っています。
生後1ヶ月程度のあまりに早い時期に親兄弟から離されてしまうと情緒不安定になりやすく、犬同士の付き合い方を学ぶことができなかったために、他の犬を見るたびにケンカをしたり、必要以上に怯えるなどの問題が起こりやすくなります。
また攻撃を抑制することが出来ず必要以上に攻撃的になったり、他の仔犬や人間の子供など、自分より弱者に対して手加減できない、寛容さを持てないなどの深刻な問題が起こる可能性も高くなります。
他にも、上下関係のルールも知らないために、しつけも難しくなる傾向にあります。
逆に生後3ヶ月を過ぎるまで人間の手に触れられることがなかったり、人間からいじめられたりした経験を持つ仔犬(捨て犬の生んだ仔犬など)の場合、人間との共同生活に馴染むことができずに持て余されてしまったり、家族である人間に対してもビクビクしながら過ごすこともあります。
新たに仔犬を迎えるならば、生後2ヶ月間は母犬や兄弟犬達と共に過ごした後、8週目~12週目(生後3ヶ月目)の時期が最適です。
この頃は、ちょうど社会化期の後半にあたり、母子以外の外部に対する社交性が集中的に養われる時期です。
▲ 順位付け -犬の反抗期?-
それまでは素直なイイコだったのに、生後4ヶ月を過ぎた頃から反抗的な行動をとることがあります。
「名前を呼んでも来ない」 「イタズラをして、叱ると唸るようになった」「お父さんの言うことは聞くのに、私の言うことは聞かない」などという行動が主なものです。
人間の子供でいえば反抗期のようなこの行動は、犬の本能による「順位付け」 によるものです。
犬の社会は完全な縦社会で、上下関係がはっきりしています。
順位が下の犬が上位の犬やリーダーに逆らうことは許されず、そのため仔犬は成長過程で自分の群れの中での位置を確認する必要がでてきます。
家庭で飼われている犬の場合、反抗的な態度をとることで、家族という群れの中でリーダーは誰か、自分はどの位置にいるのか、どこまでが許される行動なのか、ということを確認しています。
犬は、一度許された行為は 「やってもいいこと」だと判断します。
成犬になってから、人間が 「もう大人なんだから…」というように考えても、犬には通用しませんので、注意が必要です。
順位付けの行動がどのくらいの強さで出るかは、その仔犬の性格によって違いがあります。
気性が強くボス的な資質のある仔犬では順位付けの行動が激しい傾向にあり、気の弱い仔犬や従順な性格の仔犬では、目立った順位付けの行動が見られないこともあります。
※ 順位付けのための挑戦をする場合、仔犬はまず自分と最も近い立場の相手に向かっていきます。
小さな子供のいる家庭では、その最初に向かって行く相手として、子供が選ばれてしまうことが多くあります。
子供だけに飛びつく、唸る、噛みつく、服を噛んで振り回そうとする、などの行動は、子供に対する仔犬の挑戦ですので、大人がしっかりとした対処をしなくてはいけません。
権威あるリーダーとして、子供を甘く見ている仔犬の態度を叱り、同時に子供にも正しい犬との接し方を教える必要があります。
仔犬に追いかけ回される子供の姿を見て、ほほえましいと笑ったり、仔犬をほめるような態度を見せることは厳禁です。
また、子供を追い掛け回す仔犬を、さらに大声をあげながら追いかけるような行動は最悪です。
3.思春期~成犬
▲ 性成熟と去勢・不妊手術の時期
生後6ヶ月~1年の間に、仔犬は性成熟を迎えます。
性成熟の時期には個体差がありますが、一般的に小型犬ほど早く、大型犬や超大型犬は遅くなる傾向にあります。
(時には、2才を過ぎるまで性成熟しない場合もあります)
メスならば最初の発情を迎えることで、性的に成熟したことがわかります。
オスの場合にはいつ性成熟を迎えたかの判断は難しくなりますが、片足を上げてオシッコをするようになったら、性的に成熟したと判断されます。
去勢・不妊手術を考える場合には、あまりに早い時期で手術をするとホルモンのバランスが崩れ、成長不良や精神的に不安定になるなどの弊害が出ると考えられているので、ある程度性成熟を迎えてから、ということになります。
目安としては、メスでは最初の発情が終わってから。
オスでは肢をあげてオシッコをするようになってから、となります。
(共に、生後7~10ヶ月頃)
ただし、室内飼いをしているオスの場合、室内でマーキングをするようになっては困るということがあります。
そのような場合には、かかりつけの獣医師に事情を説明し、相談の上で手術の時期を決めてください。
▲ 繁殖する場合の時期
もしも繁殖を考えるならば、特にメスならば体が十分に成長し、体力のある1~4才までの間が最適とされています。
最初の発情の時期 (大体生後8~10ヶ月)では、まだ体も十分に成長しきっていないために母犬への負担が大きすぎ、胎児への悪影響も考えられます。
(そのため純血種の犬では、母犬が生後9ヶ月未満で出産した場合、仔犬には血統書は発行されません)
逆に、年をとってから (5才以上) の初産の場合も、妊娠中毒症を起こす可能性が高くなります。
妊娠中毒症を起こすと、仔犬だけでなく母犬の生命にも危険が及びますので、無理な出産計画はやめましょう。
「まだまだ…」 「もうちょっとしてから…」と先伸ばしにしているうちに時期を逸してしまった場合は、無理はせずにお産はあきらめた方が良いでしょう。
オスの場合も、体の成長が終わってからの方が十分な精巣の機能が期待できるため、1才を過ぎてからの交配が推奨されます。
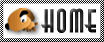
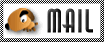
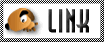


 質問は・・・
質問は・・・