しつけの基本
1.コミュニケーション
当然ですが、生まれて初めて人間と暮らす仔犬は、人間の言葉を理解できません。
「いい子だね」 とか 「悪い子だ」 と言って、人間はほめたり叱ったりしているつもりでも、犬にその意味がわかっていなければ意味がありません。
ほめたり叱ったりする時には、犬が理解できるようにすることが大切です。
そのためにも、普段から仔犬にはひんぱんに声をかけるようにしましょう。
仔犬にいろいろと話しかけていれば、自然に仔犬は人間の言葉を覚えていきます。
特に、いつも同じ言葉を同じ状況で使っていれば、仔犬はあっという間にその言葉を覚えます。
例えば仔犬の足を拭く時に、いつも 「足をあげて」と声をかけていれば、仔犬はその言葉と 『足を上げる』行動を結びつけて、自然と自分から足をあげて拭いてもらうようになります。
また、ひんぱんに話しかけられているうちに、自然と仔犬は『人間の言うことに集中する』 癖がついていきます。
人間が話すこと、言うことに集中するということは、しつけを行う上で非常に有効です
2.「ごほうび」 と 「罰」
▲ アメとムチ
犬をしつける時には、犬が人間の望んだことをした場合(例えば、「オスワリ」 と言って座った時)にはごほうびを与え、望まないことをした場合(イタズラなど) には罰を与える方法をとります。
犬は意外と合理的な性格をしています。
何かした時に、自分にとって嬉しいことや都合のいい事が起こったら、何度も同じ事をくり返します。
逆にイヤなことがあったり、イヤな思いをしたことは、段々としなくなっていきます。
「ごほうび」 とは犬にとって嬉しいことです。
言葉でほめる事の他に、なでてもらう、一緒に遊んでもらう、オヤツをもらう、などが当てはまります。
特にオヤツは効果的です。
いつも食べているフードの一粒でも、犬にとっては嬉しいオヤツで、十分なごほうびになります。
食べ物で釣るようで抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、オヤツはごほうびとしては、犬が最も理解しやすいものです。
普段の生活の中で漠然とオヤツを与えるよりも、ごほうびとしてオヤツを与えることは、犬にとっても生活にメリハリがついて、プラスになります。
(ただし、与えすぎには注意してください)
「罰」 は犬にとってイヤなこと、イヤな思いをすることです。
叱られる、無視されるなどの他に、急に大きな物音がしてビックリするのも、罰になります。
間違えないで欲しいのは、罰はあくまでも犬がイヤな思いをすれば良いので、苦痛を与える必要はないということです。
言う事を聞かなかったり、イタズラをしたからといって、叩くのはやめましょう。
仔犬が人間の手に対して恐怖感を持ち、最悪の場合人の手を噛むようになってしまいます。
▲ ほめる時
犬は人間の口調や声のトーンに非常に敏感です。
高い声や明るいトーンの声を聞くと、ウキウキして、楽しい気分になります。
ほめる時には、なるべく高めの声でほめてあげましょう。
同時に耳の後ろなどの犬の喜ぶところをなでてあげたり、少量のオヤツやフードを与えるのも効果的です。
大切なのは、気持ちをこめてほめることです。
仔犬が言う事を聞いてくれて、あなたが喜んでいることを、素直に伝えましょう。
気持ちのこもらない言葉だけでは、ほめていることにはなりません。
特に、教えた事を初めてできた時には、思いっきりほめてあげてください。
ほめられたことが理解できていれば、犬も満足そうな表情をします。
口を開け、目を細め、耳が後ろに引かれた表情は、「笑顔」そのものです。
もちろん、尻尾を大きく振るのも、嬉しい時の表情です。
逆に、ほめているつもりでも、うつむいてうなだれたような表情をしていたり、尻尾が力なく垂れ下がっているような時は、ほめられていることを理解できていません。
そんな時は、なるべくオーバーにほめてあげるようにしましょう。
▲ 叱る時
ほめる時とは逆に、低めの声で叱ります。
ヒステリックに高い声で叱りつけたり、追いかけ回したりするのは逆効果。
仔犬は興奮して、遊んでくれていると勘違いしてしまいますので、特に女性は気を付けてください。
ぐちぐちと文句を言うのも効果はありません。
叱る時には冷静に、ビシッと一言で決めましょう。
また、言葉で叱るのと同時に、仔犬の鼻先を軽く握ったり、体を上から押さえ込んだりして、仔犬の動きを拘束するのも効果があります。
(非常に気が強い仔犬だと、怒って反撃してくる場合があります)
そして、叱る時にはなるべく同じ言葉(「いけない」「ダメ」など)を使って叱るようにしましょう。
その言葉と叱られたことが結びつき、徐々に言葉の制止だけでも理解できるようになります。
他に、『天罰方式』 と呼ばれる方法も有効です。
イタズラをしている時に、いきなり大きな物音がしたり水をかけられるなど、犬にとってイヤなこと(この場合はビックリすること)が起こる、というものです。
よく使われるのは、空き缶に小石を入れてガムテープなどで封をしたものを、犬の足元に投げつける方法です。(ぶつけてはいけません)
ただし、『天罰方式』 で大切なのは、誰がやったのかわからないように犬を驚かせることです。
あくまでも「どこからともなくイヤな事が降ってわいた」と思わせることが大切ですので、そのイヤな事の原因が飼い主だと悟られては意味がなくなってしまいます。
イタズラなどに熱中している時に、後ろから、あるいは物陰に隠れて『天罰』 を与えてください。
3.犬がしつけを理解するしくみ
▲ 条件付け(習慣付け)
犬が物事を覚える基本となるのは、条件付けです。
例えば…
名前を呼ばれて、寄って行ったら嬉しいことがあった (ほめられた、オヤツをくれた、遊んでくれた、など)
⇒ 次もやってみようかな? スリッパをかじっていたら、イヤなことがあった (叱られた、無視された、など)
⇒ しちゃいけないのかな?
仔犬のいろいろな行動の中から、ずっと続けて欲しいものに対しては常にほめ、仔犬を勇気づけましょう。
逆に、やって欲しくないことは仔犬の時から叱るなどして、早めにやめさせるようにします。
その他、毎日の暮らしの中で、同じ状況で同じ行動をしていれば、それが習慣となり、その行動を覚えていきます。
例えば室内飼いの場合、散歩から帰ってきたら常に足を拭いてから家の中に入れるようにしていると、「散歩から帰ったら、足を拭かないと家に入れない」というように覚えて、大人しく足を拭かせるようになります。
▲ 反復
条件付けしたことを何度も繰り返すことで、完全に理解させていきます。
名前を呼ばれる度に寄って行くと、いつも嬉しいことがある
⇒ 名前を呼ばれたら、飼い主の所へ戻るということを覚えます。 スリッパをかじっていると、いつもイヤなことがある
⇒ スリッパをかじるイタズラをしないようになります。
反復は、完全に理解するまで毎回続けることが大切です。
犬種や性格によって、完全に理解するまでにかかる時間は違いますが、仔犬の時期は特に順応性に優れているので、人間があきらめなければ、必ず覚えてくれます。
4.しつけをする時の注意
▲ 統一することが大事
「やっていいこと」 と 「悪いこと」 は、常に一定にしてください。
同じイタズラをしても、気分で叱ったり叱らなかったりでは、仔犬が混乱してしまいます。
いつまでたってもイタズラをやめないばかりか、家族に対して不信感を持つこともあります。
ほめる事はほめる、叱る事は叱る、ケジメをつけましょう。
また家族によって、叱ったり叱らなかったりというのも、混乱の元です。
例えば…
お母さんは毛がつくからソファには乗って欲しくなくて叱るのに、お父さんはソファに乗っても叱らない… というのでは、仔犬はいつまでたってもソファに乗るのをやめません。
挙句の果てに、お父さんが留守の時はソファに乗らないのに、お父さんが帰ってくると乗る、というように、人を見て行動するようになってしまいます。
このような事態を防ぐためにも、家族で話し合って、「やっていいこと」と 「悪いこと」 をしっかりと決めてください。
▲ リーダーシップを取る
犬のしつけをするためには、人間 (飼い主)が犬にとっての良いリーダーにならなくてはいけません。
リーダーだと感じているからこそ、犬は飼い主の言葉に耳を傾け、いいつけに従うのです。
では犬にとって 『良いリーダー』 とはどんな飼い主でしょう?
▽生活のルールを作る▽
食餌や散歩は、犬にとっては一大行事であり、大きな楽しみであり喜びです。
大切な食餌や散歩を与えてくれるのがリーダーというわけですが、食餌や散歩など、生活のリズムを作るのはリーダーである飼い主です。
犬が吠えるなどして食餌や散歩を催促することがありますが、『催促されて、犬の望みをかなえる』というスタイルではいけません。
犬は 『催促すれば、自分の望みがかなう』 と覚えてしまい、ひいては 『自分の方がエライ』 と考えるようになってしまいます。
犬の都合に振り回されないよう、注意してください。
朝、起きる時間を決めるのも、食餌の時間も散歩の時間も、決めるのはリーダーであって、犬ではありません。
▽一貫性を持つ▽
その日の気分で、仔犬への接し方を変えてはいけません。
機嫌がいい時には仔犬が何をしても叱らず、逆に機嫌が悪い時はちょっとしたことで仔犬を叱りつけるような接し方は、最悪です。
自分の気分とは関係無く、いい事はいい、ダメな事はダメという善悪のけじめは、しっかりとつけましょう。
▽犬の流儀を理解する▽
犬のことを何も知らずに、「あれはダメ」 「これもダメ」と人間の都合ばかり押しつけてはいけません。
犬についても、きちんと理解するようにしましょう。
どうしても直らないイタズラや困った癖も、犬の習性が原因になっている場合があります。
犬の生活習慣や習性をきちんと理解した上で、解決法を探しましょう。
▽犬の愛情表現をイヤがらない▽
特に仔犬は、相手の顔をなめようとします。
これは仔犬が目上の相手に対して行うアイサツであり服従の表現ですので、振り払ったり叱ったりしてはいけません。
顔をなめられるのがイヤでしたら、かわりに手をなめさせるなどして、きちんと仔犬の愛情表現を受け止めてあげてください。
また飛びつく仔犬に対しては、飛びつく前に「マテ」 をさせて、やめさせましょう。
(仔犬が飛びつくのをやめたら、必ずほめてください)
大型犬の仔犬の場合、体はどんどん大きくなっても、中身は仔犬のままですので、やはり飛びついたり顔をなめようとします。
この時に、絶対に怖がったりしてはいけません。
一瞬でも仔犬に対して 『怖い』 と感じてしまうと、仔犬は『自分の方が上』 だと感じて、飼い主を見下すようになってしまいます。
飼い主が犬にとって、『頼りになる大好きなリーダー』であれば、しつけ上の問題はほとんど起こりません。
そして、飼い主が犬にとっての 『良いリーダー』になるためには、日常生活でのちょっとした注意さえしていれば、特に難しいことではありません。
言いかえれば、仔犬を飼い始めた当初からけじめのある生活をしていれば、それが自然と仔犬のしつけになっているハズです。
▲ 1回叱ったら、3回ほめる
人間だって、叱られてばっかりではやる気をなくしてしまいます。
犬も同じで、特に仔犬は、叱られてばかりだと愛情を感じることができません。
落ち込んだり拗ねたりしてしまい、飼い主に対して不信感さえ持つようになってしまいます。
1回叱ったら、3回くらい誉めてあげましょう。
ですが、ただ誉めたりなでたりしても効果はありません。
仔犬のイタズラを叱った後には、「オスワリ」「おいで」 などの仔犬が既に出来ることをさせて、誉めてあげるようにします。
そうすることによって、仔犬の沈んだ気持ちをフォローすると同時に、「いいつけを守れば、良いことがある」という理解を強化させることができます。
特に気の弱い仔犬は叱りっぱなしにせず、十分にほめて、気分的なフォローをしてあげましょう。
また、なるべく仔犬を叱る状況を減らすようにすることも大切です。
人間が先回りして仔犬のイタズラを未然に防ぎ、覚えてほしくない事やしてほしくないイタズラは、最初からさせないように心がけましょう。
覚えてしまったイタズラを叱ってやめさせるよりも、仔犬がイタズラをしない状況を作る方が、仔犬にとっても人間にとっても、ずっとストレスが少なくて済みます。
例えば、仔犬がいつもスリッパをかじってしまうならば、仔犬が取れない場所にスリッパをしまっておけば、仔犬はスリッパをかじることはできませんよね?
部屋の整理整頓を心がけ、仔犬にかじられては困る物、仔犬に壊されたら困る物は、きちんと片付けておきましょう。
とても単純な事のように思われるかもしれませんが、仔犬のイタズラを防ぐには、非常に効果的です。
また仔犬がイタズラしては困る物 (ゴミ箱など)に近づいたら、「いけない」 と注意したり、仔犬のお気に入りのオモチャを見せて興味をそらす方法もあります。
そのためにも、仔犬が特に気に入っているオモチャはしまっておいて、特別な時だけ遊べるごほうびとして利用すると良いでしょう。
▲ あせりは禁物! そして初志貫徹
人間の子供だって、生まれたばかりの赤ん坊の時は、言葉を理解することも話すこともできません。
数年かかって言葉を覚えるように、犬も今日教えたことが明日すぐにできる、というようにはなりません。
近所で見かけるお利口なワンコも、TVなどで見る盲導犬や警察犬なども、一朝一夕にできあがったものではありません。
飼い主や訓練士との信頼関係をしっかりと築いた上で、毎日毎日同じ事を繰り返し、少しずついろいろなことを覚えて、賢いワンコに成長したんです。
犬にも覚えの早いコもいれば、なかなか覚えてくれないコもいます。
しつけをするには、仔犬の性格を読み取って、そのコにあったやり方をすることが必要です。(参照:「しつけを始める前に」)
でも、あまり難しく考える必要はありません。
大切なのは、そのコに対して愛情をもち、きちんと理解してあげることです。
一方的に人間のルールや都合だけを押しつけてもいけませんし、かと言って、むやみに甘やかしてもいけません。
犬が持つルールやそのコの気持ちも考えて、お互いに歩み寄ることが必要です。
たとえ時間がかかっても、犬との信頼関係がきちんとできていれば、必ず犬は答えてくれます。
『うちのは、ダメ犬』 などと投げ出したりしないで、根気よくしつけをしましょう。
毎日続けたしつけの結果は、仔犬が1才、2才と成長した時に必ず実を結びます。
ただ、しつけの練習をする時にはあまりダラダラとやっていても、犬の集中力はそれほど長く続きません。
最初は1~2分間、一日数回に分けて行います。
(一日一回でも、必ず毎日続けてください)
また、「よく頑張ったね、イイコだったね」とほめる意味で仔犬と遊んでから、しつけの時間を終わらせましょう。
仔犬の表情を観察することも大切です。
名前を呼んでもそっぽを向いていたり、上目遣いに、さぐるように見返したりするのは、「飽きている」「落ち込んでいる」 というサインです。
そのような時は、早目に練習を切り上げたり、気分転換に一緒に遊ぶなどして、仔犬の気分を盛り上げてあげましょう。
あせらず、欲張らず、こつこつと!
1回叱ったら、3回誉める。
忘れないでください。
飼い主とワンちゃんとのマナークイズ
まずはワンちゃんとみなさんのマナーについてクイズを出しますので、○×で答えてみてくださいね。
1. 人けの無い夜間なら、散歩がわりにリードをはずして家の外へ放してやっても良い。
2. 番犬になるので、客にはできるだけ大きな声でしっかりと吠え続けるほうが良い。
3. ブラッシングは、風通しの良い庭やベランダなどでするほうがよい。
4. 小型の室内犬は、運動がいらないので散歩をする必要がない。
5. 散歩中に他のワンちゃんを連れた人に出会ったら、まずワンちゃん同士をご挨拶させる。
6. マーキングは、犬の本能なので、どこでもできるだけ自由にさせてやるほうが良い。
7. ウンチをしたら、きちんと埋めて帰る。
8. 公園に誰も居ない時にはリードをはずして自由にさせてやっても良い。
9. 発情中のワンちゃんでも、パンツを使用すれば公園などへ連れてきても良い。
10. ドッグランでは、中にいる犬が少ない時は、すぐに犬を放しても心配ない。
正解は・・・・すべて、× です。
「こんなこと、あたりまえでしょ!」と思うようなことも、自分ではなかなか気づかないでいることも、犬との暮らしの中で守らなければならないマナーって、実はたくさんあるんです。
あなたにとってかわいいワンちゃんが、他の人には密かに眉をひそめさせる不愉快なものになったりしないように・・・そう、世の中、犬の好きな人ばかりじゃないですからね。
その「犬嫌い」を増やしているのは、実はマナーの悪い「愛犬家」であることが多いんです。
みなさんは、ぼくらワンコに「しつけ」ってするけど、あれは何のためだと思いますか?
「オスワリ」や「フセ」「待て」などを覚えるのは、それ自体が目的なんじゃないんです。
犬の好きな人も、嫌いな人も、無関心な人も、いろんな人がいる社会の中で、迷惑をかけることなく気持ちよく一緒に暮らすための「マナー」を実践する手段なんです。
あなたとワンちゃんが誰からも好かれるステキなパートナーでいるために、家で、散歩の途中で、公園で、ドッグカフェやドッグランで、どんなことを、気をつけなければいけないのか、マナーの基本について、これから一緒に勉強しましょう!
▲ おうちで守るべきマナーって?
まずは、ワンを家の敷地外に放し飼いにしないことが、最低限のマナー。
昔は、よく散歩代わりに門の外に放される子もいたけど、犬の嫌いなご近所さんにとっては、これほど不快なものは無いです。あちこちに排泄しっぱなしで、ゴミを荒らしたり、車の事故に遭うかもしれないし、よその犬とけんかしたり、妊娠したり、させちゃったり・・・ロクなこと無いんです。自宅の敷地からワンちゃんが脱走しないようにきっちりと環境整備することも大事です。
いざという時のために、連絡先を書いた名札を首輪につけておくことも必要です。
ちょっとした油断がもとで迷子になっちゃって、保健所や愛護センターに収容される子がどれほどたくさんいることか・・・
万が一迷子になってしまった時は、すぐに最寄の警察、保健所、愛護センターなどの収容施設に連絡しておきましょう。
家族の一員であるワンちゃんの命に責任を持つこと、それはマナー以前に必要な飼い主としての使命なんです。
それからもちろん、吠え声やニオイ、抜け毛などでご近所に迷惑がかからないように配慮しなくちゃいけません。
無駄吠えしないようにしつける、排泄物はちゃんと処理する、ブラッシングは外に毛の飛び散らない場所でするなど、飼い主としてやるべきことはきっちりとやりながら、ご近所さんにも、ワンちゃんのことを紹介して仲良くなってもらったり、普段から、まわりの人とのコミュニケーションを大事にすることも、いざという時、トラブルの種を大きくしないために必要です。
▲ お散歩に行こう
ワンコにとって、飼い主のみなさんが思っている以上にお散歩はとっても大事なことなんです。
運動のためだけじゃなくて、頭と身体にたくさん刺激を受けて、気分転換したり、社会勉強したり、飼い主さんとのコミュニケーションのためにも必要なことなんです。
小さいうちから、色んなところへ行って、いろんな人やワンちゃんに会っていろんな楽しい体験をすることは、ワンの心を明るくおだやかに育てて、みなさんと一緒に社会で暮らしやすくすることになるんです。
反対に、いろんなものに出会う機会がなかったり、あってもそこで怖い思いや嫌な思いを重ねていると、どこへ行くにも誰に会うにもビクビク臆病になったり、怒りっぽくなったりなかなか素直に受け容れられないワンコに育ってしまうことが多いです。
そんなふうにいろんな経験の中で心を安定させることは、実はしつけ以上にとっても大事なことだから、忘れないで下さい。
この頃は、お散歩に連れて行ってもらえない小さい仲間も多いようですが、外でしっかり発散しなきゃ、しつけの勉強にだって集中できないはずです。
▲ 出かける前に、忘れず持ったかな?
さて、散歩に出かける前に絶対に忘れないでほしいことがあるんです。
それは、ウンチを拾うための袋を持って行くこと。
ちゃんと拾って持って帰らないと、バイ菌の巣になって不衛生だし、後から歩く人やワンちゃんが踏んじゃうし、飼い主のウンチの不始末が原因でワンが立ち入り禁止になってしまった公園も多いんです。
ちょっとくらい、自分一人くらい・・・って思ってたらNO!
▲ オシッコする場所は考えて
オシッコやマーキングは、場所をわきまえてやらなくては。
よその家の前や、塀、子供たちが集まる公園の砂場や花壇や芝生なんかにされたら、臭くて不衛生だし、芝生や草は枯れちゃうし、気持ち悪くて絶対イヤですよね。
マーキングは、ワンコにとって、公共の掲示板に書き込みをするようなものなんですが、誰かが一度書き込むと、上からドンドンいろんなワンコが書き込みたくなっちゃうから、シミもだんだん濃くなってニオイもきつくなってきちゃいます。
だから、ほんとはペットボトルに入れたお水を持っておいて、書き込みの上からかけて消しておくとベターです。
そんなふうにしてたら、みんななんてスマートな飼い主さんなんだろうって感動すると思います。
▲ しっかりと、つないだ手は放さない
これも絶対に守って欲しいこと・・・
それは、リードをつけて絶対にはずさないこと!
首輪も、とっさの時に抜けちゃうことのないよう、きちんと確かめて調節しておく。
刺激の多いところでは、どんなにお利口のワンコにだって不慮の事態というのは有りうります。
路地から急に飛び出してきた子供や自転車におどろいて、とっさに飛び出た道路で車に轢かれる・・・なんてこともあるかもしれない。
他の動物や動くものに挑発されて、思わず追っかけたり飛びつきたくなるかもしれないし、逆に、他のワンコに追っかけられても助けられないですよね。
知り合いのワンにも、散歩中の公園でノーリード(引き綱をつけていない野放し状態)でいる時に、大型犬に追いかけられてかみ殺されちゃった子がいるんです。
悲しいことに、そんな事故は、この頃めずらしくないらしい・・・
そう、ワンにとって、リードは飼い主にあずけた「命綱」でもあるんです。
それに、犬が怖かったり、嫌いだったりする人にとっては、ノーリードの犬ほど脅威に感じるものはないんです。
よく、「うちのワンちゃんは何も悪いことしないから大丈夫。」って、公園で放したりする人いるけど、世の中、犬好きばかりじゃないですからね。
ちゃんとルールを守って、ワンコの苦手な人にも受け容れてもらえるような飼い方をしないと、ワンは嫌われ者になっちゃって、「犬と人が一緒に楽しく暮らす」社会なんて実現しないです。
そのためにも、公共の場できちんとリードをつけることは、「わたしたちはちゃんとルール守って暮らしています」というアピールでもあると思うんです。
ワンの安全と、みんなの安心と、「犬と人の共生社会」実現のためにも、リードでつないだ手は絶対にはなさないで!
▲ ワンちゃん同士、ちゃんとごあいさつできるかな?
先日のこと、散歩の途中で出会ったワンちゃんが、いきなり飼い主さんを引っ張りながらワンのほうに突進してきて、ちょっと小心者だからものすごく怖くなって思わず大きな声で吠えちゃいました。
そしたら向こうのワンちゃんもますます興奮しちゃって、危うく喧嘩になるところだった・・・。
みなさんのワンちゃんは、こんな怖い思いをしたりさせたりしたことはないですか?散歩の途中や公園で他のワンちゃんに会った時、どんなふうにご挨拶してますか?初めて会うワンちゃんには、ワンちゃん同士をいきなり近づけたりしないようにしましょう。
まず、相手の飼い主さんに挨拶をして、自分の犬を近づけてご挨拶させていいかどうか、ちゃんと聞いてからです。
小心者のワンには、あいさつするにも心の準備や飼い主の手助けがいるかもしれないし、相手はとっても怒りんぼうの荒くれワンコで、近づくといきなりガブッ!なんてこともあるかもしれないですから。
相手の飼い主さんが許してくれたら、お互いに匂いを嗅ぎあえる距離までゆっくりと近づける・・・
どちらかのワンちゃんが、極端に嫌がったり、怒ったりしていないか、ちゃんと見てあげながら、無理は禁物です。
こんな出会いの時に怖い思いをしたことがきっかけで、他のワンちゃんが苦手になってしまう子が実はとっても多いんです。
▲ 人とワンちゃんのご挨拶
飼い主のみなさんとよそのワンちゃんが気持ちよくご挨拶するにはどうすればいいのか、知ってますか?
「かわいい~」なんて言いながら、いきなり頭撫でてくる人がありますが、ワンはとっても苦手です。
ワンコはみんな、上から覆いかぶさるようにのぞきこまれたり、頭の上から手をかざされたりするのがとっても嫌なんです。思わず警戒してあとずさりしたくなります。
よそのワンちゃんに挨拶する時は、できれば正面からじゃなくて、ワンちゃんに向かって少し斜め方向に位置をずらす感じで、ゆっくりと近づいて欲しいです。
これは、犬同士が出会った時も使っている、相手や自分を安心させるための合図(カーミングシグナル)なんです。
そして、グーに握った手をワンちゃんの下の方からそっと差し出して、その手の匂いを嗅がせてほしいです。
これは、「私、こういう者なんですが・・・」って、名刺を差し出すようなものかな。怖がりの子には少し視線をずらしたり、ちょっと離れた場所で、ワンちゃんの方から近づいて来るのを待ってあげるのもいいですね。ワンちゃんが、その手の匂いを嗅いで関心を示してくれるようなら、そっと首の側方から胸の前辺りにかけて撫でてあげる。決して頭の上から撫でたりしないように!
こうして“礼儀正しく”ご挨拶してくれたら、きっといいお友達になれるはずです。
▲ 苦手な犬や人とすれ違いたい時は
ご挨拶ができない、あるいはしたくないって時には、どうやってすれ違いますか?
とにかく、避けたいものは、できるだけ早く飼い主さんが先に発見して心の準備をして欲しいです。トラブルは、起こってから解決するのではなく、起こらないように努力することが原則です。
避けたいものから道をはずして遠回りすることもOKだし、ワンちゃんを避けたいものと反対の側に付けて、近づく前から、注意をそらしながら、少し大回り気味にすれ違うなどしてみましょう。こんな時にこそ、アイコンタクトや「ツケ」が役に立つんです。
落ちているものや、道の傍にあるもの、例えば、落ちてる食べ物や、庭先につながれて吠えているワンちゃんなどの傍を通る時も同じです。
無事にお利口で通りすぎることができたら、ちゃんとしっかりほめてあげてください。
▲ ドッグカフェでお行儀よく
最近は、飼い主さんと一緒にお出かけできるところが増えて、楽しみも増えてきましたよね。
飼い主さんと入れてお茶や食事も楽しめる「ドッグカフェ」って行ったことありますか?
普通のカフェやレストランでも、ワンを入れてくれるところが少しづつだけど増えてます。
でも、反対に利用する飼い主さんやワンちゃんのマナーの悪さが問題になって、ワンが入れなくなってしまったところもいっぱいあるんです。
そんな残念なことにならないように、カフェやレストランをワンと一緒に利用する時のマナーについて、基本をしっかり押さえて心得ておこう!
さて、一口に“犬連れOK”と言っても、ワンちゃん連れのために作られた「ドッグカフェ」と、普通のカフェ・レストランだけど、ワンちゃん連れも利用してよいことになっているところとがありますよね。
いずれも、ワンの入れる場所が決まっていたり、予防接種済みの証明が入店に必要だったり、その他のマナーについても、そのお店なりの決まりのあるところが多いので、実際に訪れる前に、必ずちゃんと確認しておくように。
多少未熟者のワンコでも大目に見てくれる店は多いですが、「ドッグカフェ」と言えども、基本的にはヒトが食事やお茶を楽しむ場所だから、衛生面の配慮や、食事をする場にふさわしいマナーを心がけることが必要です。
犬の苦手な人が同席しても受け容れてもらえるマナーの良さ・・・これをめざしてください。
そのためにも、これからお話しすることは守れるよう、がんばってみてくださいね。
1. まず、お店に入る前に必ずトイレは済ませておこう。
おもらしやマーキングの心配な子は、「マナーベルト」を使うと安心です。
万が一、失敗してしまった時は、お店の人にも断って、ちゃんとふき取って消臭しておきましょう。
2. 店内ではちゃんとリードを着用しておくこと。
お店によって看板犬はノーリードのところもあるけど、他のワンちゃんやお客さんへのマナーを考えると、やはりリードを着用しなくては。
3. 飼い主さんが食事やお茶を楽しんでいる間は、リードを備え付けの金具につなぎ留めるか、ちゃんと手に持って、ワンちゃんは、飼い主さんの足元に伏せをさせておけるとベストです。
伏せておくのが無理でも、リードは短く保っておいて、周りをウロウロできないようにしておきましょう。
入店前に、散歩などでしっかり発散させておけば、自然におとなしくおりこうにできるようになるものです。
4. 吠えてうるさくするのもマナー違反です。周りの人への気配りも忘れずに。
5. お店によっては、ワンを椅子の上に座らせてくれるところもありますが、“椅子”は本来ヒトのための場所、汚れたり、毛がついてしまったりすると、犬の苦手な人にはきっと歓迎されないです。
どこでも通用するマナーを身につけるには、他の場所で混乱しないように、椅子には乗らないほうがいいかもですね。
6. テーブルに足をかけるのもご法度です!食べ物を置くところですからね。
7. どんなに欲しがっても、ワンコに人間の食べ物をあげてはいけないです。くせになっちゃって、おとなしく待ってられなくなっちゃいますから。
ワンちゃん用のメニューがあるところでも、人間用の食器やスプーンなどをワンコに使ってはいけない、これ、常識ですね。
8. 店内で他のワンちゃんとご挨拶させる時は、お散歩や公園の時と一緒だよ、先に飼い主さんにひとこと声を掛けてからにしましょう。
ご挨拶の後も、はしゃぎ過ぎには注意だよ、場所をわきまえよう。
9. 発情中のワンちゃんは、残念だけど、他の子に迷惑かかるから、完全に落ち着くまで、カフェやランなどたくさんのワンちゃんの集まる場所へは出入り禁止!店内の、犬が入れる場所、入れない場所を確認しよう。
▲ ドッグランを楽しもう
ワンの自由広場、「ドッグラン」。思いっきり走りまわれますね。
でも、いろんなワンちゃんが集まる場所だけに、きちんとマナーを守って遊ばないと思わぬ事故やトラブルにもつながりかねないです。
健康状態には気をつけて、皮膚病やノミ・ダニなどの感染症をやりとりしないように注意しよう。
1. ランに入る前に、どんな仲間が来ているのか、ちょっと様子を伺ってみる。
知らないワンちゃんがいる時は、中に入ってしばらくはリードをつけたままで様子を見て、上手にあいさつして遊べそうだったら放してあげるようにしよう。
先にランに居たワンちゃんたちも、新しい子が入って来る時は、ちょっと注意してあげよう。
どちらかが極端に怖がっていたり、興奮し過ぎていたりする時は、飼い主さんがちゃんと間に入って援助してあげる。
2. いざというときのために、名前を呼んだり「おいで」などのコマンドでちゃんと呼び戻しができるようにしておくほうがいい。
ランで遊んでる最中にも、時々呼び寄せて、傍に来たらほめたりごほうびのおやつをあげたりして練習してみてください。
3. ランの中で自由にさせている間は、いつ、どんなことが起こるかわからない・・・。
他のワンちゃんとトラブルにならないか、どこかでマーキングやウンチをしてしまわないか、飼い主さんには自分のワンちゃんから絶対に目を離さないでちゃんと見ていて欲しいです。
ワンちゃんほったらかしでトイレに行っちゃうなんて、絶対にダメ。
4. 自分のワンちゃんのウンチはきちんと拾ってね、これ、常識です。
本当は、オシッコにもお水かけて流しておくといいですね。
5. どんなに欲しがっても、よそのワンちゃんに食べ物をあげないように。
しつけの面でも好ましくないし、アレルギーなどで食べものに制限のある子もいるので。どうしてもって時は、飼い主さんにちゃんと確認して許可をもらってから。
6. 発情中は、他の子を刺激して迷惑がかかるから、落ち着くまで来ちゃダメ。
男の子も、他のワンちゃんにマウンティングしたりしないように注意する。
あまりしつこくするようなら、そのワンちゃん自身にとってもストレスになることだから、残念だけど他のワンちゃんと一緒のランの利用は見合わせたほうがいいかもしれないですね。
7. 個人所有の囲われた敷地や「ドッグラン」以外では、公園や河川敷など、どんなに広い場所でも、絶対にノーリードで走らせてはいけない。
そんな場所でのびのびさせたい時には、他の人に迷惑にならないことを確認してから“ロングリード”を着用しよう。
▲ そして、もうひとつ大切なこと
ワンが社会で人と一緒に暮らすためのルールって、ホントいろいろあるんです。どれも人に迷惑をかけないで、ワン自身も楽しく過ごすために必要なことなんだけど、もうひとつ、忘れてほしくないとっても大事なことがあるんです。
それは、ワンコが誰からも好かれる存在でいられるように、飼い主さんたちが、ストレスをかけない優しい方法で関わってくれることなんです。
人間だって一緒でしょ、思いやりは優しさを生み、怒りは憎しみを生み出す・・・
ワンのこと、ちゃんと知って理解して、いろんなことをワンにわかりやすい優しい方法で教えてほしいんです。
決して、叩いたり、怒鳴ったり、力にまかせて無理やりな方法で押し付けたりしないで・・・
ワンが嫌われる一番の原因、「うなる」「噛み付く」は、そんな飼い主さんの関わり方が原因になってることも多いんです。
ワンが気持ちよくマナーを身につける助けになる「陽性強化法」っていうしつけの方法もあるから、我流で「こんなはずじゃなかった・・・」なんてことになる前に、ちょっとお勉強してもらえると、うれしいです
しつけを始める前に
1.何を 『しつけ』 と言うのか
▲ 『しつけ』 と『芸』 の違い
犬を飼うと、多くの飼い主が必ずと言っていいほど、ゴハンの前に「オスワリ」 や 「オテ、オカワリ」 あるいは「チンチン」 をさせています。
そして、それが 『しつけ』 だと思っているようです。
ですが、「オスワリ」 は別として 「オテ、オカワリ」などはしつけではありません。
これらは 『芸』 または特技です。
『しつけ』 というのは、犬と人間が一緒に快適に暮らすために、犬にある一定のルールを教えるものです。
例えば 「人間を噛んではいけない」 とか 「うるさく吠えてはいけない(吠えても、飼い主の注意や合図で吠えるのをやめる)」などといったものです。
つまり、飼い主の決めた生活パターンや生活のためのルールを守り、飼い主の指示に従うようにすることが『しつけ』 です。
▲ しつけられた犬って、どんな犬?
町で見かけて、「お行儀がいい」 と感じるような犬は、全てきちんとしつけられていると言って良いでしょう。
例えば…
▽飼い主を引っ張ることなく、横を並んで歩く。
▽飼い主が散歩中に知り合いと立ち話を始めても、足元で大人しく待っている。
▽他の犬と会っても、唸ったり吠えたりしない。
こういう犬達を見れば、「行儀がいい」 と思うでしょう。
彼らは、人間について歩くように、飼い主の指示に従うように、他の犬ともきちんとした犬づきあいができるようにしつけられています。
逆に、首輪やリードがちぎれそうなほど飼い主を引っ張り回していたり、朝早くから吠え続けている犬は、「行儀がいい」とは思えませんよね?
そして、飼い主が引きずられるようにしてついて行く姿や、朝早くに眠い目をこすりながら散歩に出かける姿は、「大変そう」に見えるでしょう。
このような犬達は、人間と暮らすためにルールがあることも、飼い主の言い付けを守らなければならないことも知らない、しつけられていない犬達です。
『三つ子の魂、百まで』
人間に対して使われるこのことわざは、犬にも当てはまります。
あどけない仔犬の頃、そのかわいさから許していた事を、大きくなってから「これはマズイ」 と慌てて直そうとしても、一度身についてしまった習慣や癖はなかなか直りません。
迎えたばかりの仔犬は、まだ人間と一緒に暮らすルールを知りません。
そのコが行儀のいい犬になるか、行儀の悪い犬になるかは、飼い主次第です。
素直で、人にも犬にも優しくできる素晴らしい家庭犬にするためのしつけは、仔犬があなたの家にやって来た時から始まっています。
そして、人もうらやむイイコにするためのしつけは、ちょっとしたツボさえ押さえておけば、それ程難しく堅苦しく考える必要はありません。
成長してから、困った癖がついてから直すのは、力も時間も、そして時にはプロの助力も必要です。
最初から 『いいこと』 だけを覚えさせるように、心がけましょう。
2.しつけを始める前の注意
▲ 十犬十色 -10頭いれば10通り-
いざ 「しつけをする」 と言っても、そのやり方や注意点などは、個々の犬で異なります。
犬種ごとに違いがあるのは当然として、同じ犬種であっても性格はそれぞれ異なります。
従順で優しいと言われるゴールデンの中にも気の強いコはいますし、一般に気が強いと言われるテリアの中にも大人しい臆病なコはいます。
しつけの基本は、良い事をした時の 『ごほうび』と、悪い事をした時の 『罰』 です。
しかし、何を一番嬉しい 『ごほうび』 と感じ、何を一番つらい『罰』 と感じるかは、そのコによって異なります。
本格的なしつけを始める前に、自分の飼っているコの性格をよく把握して、そのコにあった教え方やほめ方、叱り方をするように心がけましょう。
また、飲み込みが早くて、2~3回の練習であっという間に覚えてしまうコもいれば、何度も同じ事を繰り返して、少しずつ時間をかけて覚えるコもいます。
教え方も、真面目に集中して教えた方がいいコと、遊びながらゲーム感覚で教えた方がいいコもいます。
仔犬の反応や表情を見ながら、そのコにあったしつけ方をしましょう。
▲ まずは観察
そのコの性格を把握するためには、仔犬の行動をよく観察することが必要です。
仔犬がどんなことに興味を感じ、どんなことを嫌がるのかがわかっていれば、そのコにとって一番の『ごほうび』 と 『罰』 がどんなことなのか、すぐにわかるはずです。
音に過敏で恐がる仔犬に、ごほうびのつもりでピーピー鳴るオモチャを与えても、そのコは喜びませんよね?
また、そういう仔犬に大声を出して叱るのも、必要以上に仔犬を怯えさせ、萎縮させてしまうので良くありません。
しつけも、部屋の中などの仔犬が落ち着ける場所や雰囲気で行う必要があります。
また、好奇心旺盛な仔犬は、長時間一つのことに集中するのが苦手です。
そんなコには、邪魔の入らない静かな環境で、短時間に分けてしつけをするようにしなくてはいけません。
仔犬の行動からその性格をつかんで、そのコにあった環境・やり方でしつけをしましょう。
また、仔犬の表情もよく観察してください。
嬉しい時にはどんな表情をするのか、退屈している時の表情はどんなものかがわかっていれば、仔犬に無理をさせずにしつけを進めることができます。
犬は感じていることや気分は、表情や仕草などにストレートに現われています。
仔犬の良いリーダーになるためにも、仔犬の感情や気分を敏感に読み取って、コミュニケーションをとれるようにしましょう。
▲ 遊び方に出る仔犬の性格
仔犬の性格を把握するためには、仔犬が遊んでいる姿を観察するのが一番です。
ボールやぬいぐるみなど、初めて見るモノに対してどんな反応をするか、 性格の強さや陽気さ、気弱さなどによって明確に違いが出ます。
仔犬と一緒に遊びながら、そのコの性格や長所・短所を理解しましょう。
▽ロープのオモチャで引っ張りっこ▽
本気(ムキ)になって唸る犬は気が強いので、人間がしっかりとリーダーシップをとることが必要。
叱る時には、ビシッと叱る必要があります。
逆に、引っ張りっこをしようとしても、すぐにオモチャを放してしまうような 仔犬は、気弱なところや臆病な面があります。
仔犬が良いことをした時には積極的にほめて、仔犬が自信を持てるように、ほめて教えるしつけを心がけましょう。
特にオモチャを放した後、上目遣いでチラチラと人の顔をうかがうような仔犬は、甘えん坊なところがあります。
過度に甘やかすと、逆にワガママになってしまう危険があるので、注意が必要です。
▽音の出るオモチャを怖がって、近づかない▽
音に対して神経質で臆病なようです。あまり怖がるようなら、背中をそっとなでるなどして落ち着かせてください。
(あまり大げさにかまわないこと)
普段は、極端に声のトーンを変えないよう、なるべくゆっくりとした口調で話しかけてあげると良いでしょう。
特に叱る時には、高い声を出さないように注意して、冷静な態度で叱るようにしてください。
車や雷の音をこわがるコも多いので、録音したものを利用して、徐々に慣らすようにすると良いでしょう。
※ インターホンや電話のベルなどに反応して、吠え癖がつく可能性があります。
そのような時には、人間がどっしりと構えていて、「心配したり、怖がったりする必要はない」 ことを、理解させましょう。
▽動物の形をしたぬいぐるみ(少し大きめのもの)を置いてみる▽
すぐに近づくコは、好奇心旺盛。
好奇心からイタズラをする場合が多いようです。
逆になかなか近づこうとしないコは警戒心が強く、他の犬や人間との付き合いが苦手なコが多いようです。
警戒心が強いコは、絶対に叩かないでください。
人間の手に対して警戒心や恐怖心を持つようになり、突発的に人の手を噛むようになってしまいます。
知り合いの人に協力してもらい、家族以外の人間も怖い存在ではないということを教えてあげましょう。
▽仔犬の目の前にボールを転がしてみる▽
すぐに追いかけて、くわえたりかじったりして遊ぶ仔犬は好奇心旺盛。
人間がきちんとリーダーシップをとれば、活発で素直なコに育ちます。
しばらく様子を見て、それから追いかけ始める仔犬は慎重派。
臆病なところもありますので、叩いたりするのは禁物。
恐怖心から問題行動を起こす可能性があります。
イタズラをしない環境を人間が作ってあげるなどして、叱る回数を減らし、ほめてしつける方法をとりましょう。
どのような性格のコでも、仔犬と一緒に遊ぶ時の主導権は人間が握るようにしてください。
仔犬がオモチャを持ってきて遊びをねだっても、一度「おすわり」 などをさせて、「おすわり」 をしたご褒美として遊んであげるという形をとると、従順な性格を伸ばすことができます。
そして、自然と 「言うことを聞けば、嬉しいことがある」と覚えさせ、後のしつけをスムーズに進めることができます。
また、オモチャなどは与えっぱなしにせず、一緒に遊ぶようにしましょう。
(そうすることで、人間への信頼や愛情が育ち、人間と遊ぶのが好きなコになります)
遊びをやめるタイミングも、人間が決めます。
仔犬はあまり体力がないので、すぐ疲れてしまうものです。
気持ちは遊びたがっていても、足元がよろけたりするのは、体がとても 疲れている証拠。
無理をさせないよう、遊びをやめてオモチャを片付けましょう。
▲ マニュアル半分の心構え
最近では犬のしつけに対する関心も高くなり、本屋さんに行けば、たくさんの犬のしつけに関する本が売られています。
そして、時には図入りでそれぞれのしつけの方法が書いてあります。
熱心に勉強されている方も多いと思いますが、気負いすぎは禁物です。
あまり飼い主の肩に力が入っていると、犬(特に仔犬)はプレッシャーを感じて、萎縮してしまうこともあります。
全ての犬が、本に書いてある通りに完璧に出来るわけではありませんし、順調にしつけのステップを進められるわけではありません。
逆に飲み込みが良すぎて、ほんの2~3回練習しただけで覚えてしまい、本に書いてあるように繰り返し練習させると、飽きてしまう… というコもいます。
しつけに関して勉強するのは良いことですが、本に書いてあることはあくまでも参考です。
『こういうやり方もあるんだ』 というくらいの気持ちで読むようにするといいでしょう。
犬の個性を無視して、『本に書いてある通りにしなくてはいけない』とは思わないでください。
▲ 目標は高すぎず
一口に 『しつけをする』 と言っても、どこまでしつけをするのかは、それぞれの犬や飼い主さんの都合によって異なると思います。
また、いろいろなしつけの中には、適性が必要なものもあり、そのコの性格によって覚えるのが難しいものもあります。
例えば、公園のベンチなどに座った飼い主の足元で「伏せ」 をして待っている、という練習があります。
多くの人が行き来する公園で、じっと待っているということは、好奇心旺盛な犬(テリアなど)には非常に難しいことです。
また、フリスビーやアジリティなどのドッグ・スポーツで活躍していることが多いラブラドールの中にも、大人しすぎて競技に向かないどころか、ボールを投げても知らん顔して『持って来い』 を教えるのにも苦労することがあります。
しつけることやしつけの方法については、そのコの性格にあったこと、やり方を選びましょう。
しつけの練習は、毎日根気良く続けることが大切です。
最初からあまり目標を高くしすぎないほうが良いでしょう。
毎日の生活を快適にするためのしつけが、犬や飼い主のストレスになってしまっては、元も子もありません。
日常生活の中では、『座れ』 『待て』 『伏せ』『いけない(イタズラなどをやめさせる合図)』がきちんと出来て、留守番が出来る、散歩の時に引っ張らずに歩く、といったことができれば、まずは十分です。
3.仔犬の犬種別&性格別注意点
▲ 犬種別の特徴と注意
犬種ごとの特徴は遺伝的な要素によるものですので矯正が難しく、無理に抑えつけようとすると仔犬に余計なストレスを与えてしまいます。
しつけの上で「大変だ」と感じても、欠点だとは思わず、そのコの個性として大らかに受け止めてあげてください。
▽ダックスフンド▽
頭は良いのですが、頑固なところもあるので、しつけには少々根気が必要です。
また飼い主には忠実でも、他人への警戒心が強い傾向にあるので、仔犬のうちからいろいろな人や犬に会わせるなどして、社交性を身に付けられるようにしてあげてください。
▽テリア種▽
好奇心旺盛なので集中力を持続させるのが難しい傾向にあります。
邪魔の入らない静かな環境で、短時間ずつに分けて練習させましょう。
動くものには特に敏感に反応するので、注意を引く時には目の前で手を動かしたり、オモチャを見せるなどすると効果的です。
またカッとなりやすい性質のコが多いので、表情をよく見て、プレッシャーを与えすぎないように注意しましょう。
▽シェルティー、コーギー、ボーダー・コリーなどの牧羊犬種▽
もともと人間とチームを組んで仕事をしてきた犬種なので、従順性が高く、しつけもしやすい傾向にあります。
ただ、動くものや群れているものに強く反応するので、子供や他の犬がたくさんいる公園では気が散りやすくなります。
まずは家の中で、確実に基本のしつけをするようにしましょう。
▽ラブラドール、ゴールデンなどの、リトリーバー種▽
従順で物覚えも良いのですが、飲み込みが早すぎて練習に飽きてしまうことがあります。
表情をよく見て、あくびをしたり、つまらなそうな顔をしていたら、飽きてしまっている証拠です。
時々気分転換をさせたり、普段の遊びの中にしつけの要素を取り入れるなどの工夫が必要になります。
▽シー・ズー、マルチーズなどの愛玩犬種▽
見た目のかわいらしさから溺愛されることが多いのですが、意外としっかりした気性のコが多いようです。
「愛玩犬は訓練しづらい」という風説もありますが、人間と密着した生活をしている分、きちんとしたルールを決めていれば、自然としつけができてきます。
人を見て態度を変えたり、権勢症候群になって飼い主を甘く見たりすることがある事実を考えると、決して頭が悪いわけではありません。
どんな犬種でも、どんな性格のコでも、初めてするしつけの練習は、邪魔の入らない、気が散らない環境で練習するようにしましょう。
基本的に、家でできない事を家の外(公園など)でやろうとしても、できるはずがありません。
まずは家である程度できるようになってから、遠くに他の人や犬の姿が見える場所で練習し、次にもっと人や犬の近くで練習し… というように、段階を踏んで難易度をあげていくようにしましょう。
▲ 性格ごとの注意
遺伝的な要素である犬種の特徴とは違い、性格はある程度までは矯正することも可能です。
仔犬の性格をよく見て、よい方向へ伸ばしてあげるようにしましょう。
▽大きな音を恐がる仔犬▽
部屋の中などの、静かな環境で練習をするようにしましょう。
叱る時にも大きな声は出さず、冷静に対処するように心がけてください。
また仔犬を必要以上に臆病にさせないために、突然の物音などに仔犬がパニックになってしまっても、落ちついて仔犬の背中をなでるなどして、落ちつかせるようにしてください。
「怖いね、怖いね~」などの、仔犬のパニックをあおるような言葉をかけたり、あわてて仔犬を抱きしめたりするのは逆効果です。
▽気が弱い仔犬▽
叱られると物陰に逃げ込んでしまったり、立ちすくんでしまうような仔犬には、なるべく叱る回数を減らす工夫をしてあげましょう。
イタズラをする前に、他のオモチャなどを使って仔犬の気をそらせ、イタズラをしなかったことをほめるなどして、ほめてしつける方法をとると良いでしょう。
▽気が強い仔犬▽
叱られたり、遊んでもらえないと怒って吠えたりする仔犬には、毅然とした態度で望む必要があります。
といっても、キツク叱るのではなく、仔犬を無視します。
吠えても自分の望み通りにはいかないこと、飼い主が決めたルールを守らなければ望みがかなわないことを、しっかりと教えましょう。
▽独立心の強い仔犬▽
呼んでもそっぽをむいてそばに寄って来ないような仔犬は、独立心の強い傾向にあります。
このような犬はしつけをするのが難しいのですが、決して頭が悪いわけではなく、「飼い主の言う事を聞かなくてはいけない」という意識が非常に薄いために、なかなか飼い主の言う事を聞きません。
このような仔犬には、食餌を与える前や遊びたがっている時に「待て」などをさせて、根気良く 「飼い主の言う事を聞かなくてはいけない」と認識させていきましょう。
4.しつけをするメリット
▲ 飼い主のメリット
しつけられた犬としつけられていない犬とを比べれば、飼いやすいのは、もちろんしつけられた犬です。
朝方のまだ暗いうちからワンワン吠えて散歩の催促をされるなど、生活の中で犬に振り回されることがありません。
他の犬や子供を追いかけ回したり、やたらと飛びかかることもないので、いろいろな所へ犬を連れて出かけられます。
散歩中に知り合いと会った時も、犬に邪魔されることなく立ち話をすることもできます。
室内飼いをしているなら、落ち着いて家族で食事をすることも、安心して友達に遊びに来てもらうことだってできます。
足元で寝そべる犬を見ながら、くつろいで新聞や本を読んだりお茶を飲んだりという、外国映画で見るような犬との暮らしが、現実になります。
▲ 犬のメリット
完全に飼い主を信頼できる状態ですので、毎日の暮らしに心配や不安を感じる必要がありません。
家にいても散歩で外に出ていても、自分の身は飼い主が守ってくれると安心して過ごすことができます。
周囲に警戒する必要もなく、のんびりと外の空気やいろいろなニオイを楽しむことができます。
飼い主の言いつけをきちんと守っていれば、たくさん遊んでもらうこともできるし、家にやって来る人たちからもたくさんほめられ、いつも笑顔を向けてもらうことができます。
たっぷり遊んでもらった後には、何の心配もなくお腹を出して、ぐっすり眠ることもできます。
いろいろな所へ連れて行ってもらって、人や犬の友達もたくさんできます。
そして、ますますかわいがられ、愛情を注がれ、満ち足りた犬生を送ることができます。
トイレトレーニング
1.トイレトレーニングを始める前に
▲ トイレトレーニングの鉄則
犬を飼い始めて最初に直面するしつけの問題が、トイレのしつけです。
トイレのしつけ方は、仔犬の月齢や性格、どこでトイレをさせたいかによって色々な方法がありますが、どのような教え方をするにせよ、以下のことに注意してください。
▽失敗しても叱らない▽
トイレを教える際の基本です。
人間は 「トイレ以外の場所でしたから叱った」というつもりでも、犬がそのように感じてくれるとは限りません。
逆に 「トイレをしたから叱られた」 と感じてしまうことが多く、隠れた場所(家具の陰などの見つかりにくい場所) でするようになる可能性が高くなります。
特に、時間がたってからそそうを叱った場合、犬はなぜ叱られたのか理解できません。
絶対に叱らないでください。
▽失敗には冷静に対処する▽
これは全てのしつけをする上で大切なことです。
仔犬をほめる時よりも叱る時のほうが、どうしても人間は興奮してしまいがちです。
トイレに限らず、イタズラやそそうをした時に、人間があわてて大きな声を出したり走り寄って行くことは、犬にとっては「自分に注目してくれた」 「かまってもらえた」という誤解を植え付けてしまうことになります。
実は犬 (特に仔犬) にとって一番つらいことは、「無視される」ということです。
そのためにも、仔犬がトイレ以外の場所で排泄してしまった時には、あえて叱るのではなく仔犬の存在を無視するように、冷静に後片付けをしましょう。
▽トイレ以外の場所にされたら、すぐ掃除▽
犬は、ニオイに敏感な動物です。
前にしたオシッコなどのニオイが残っていれば、その場所でまたトイレをしようとします。
もしもトイレ以外の場所にしてしまった場合は、気付いたらすぐにきれいに拭き取り、消臭剤や薄めたお酢などでニオイが残らないように処理してください。
▽されたくない場所は立ち入り禁止▽
和室のタタミの上でオシッコをされてしまった場合、タタミの繊維にオシッコが染み込んで、いつまでもニオイが残ってしまいます。
客間など、どうしてもそそうされては困る部屋がある場合には、完全にトイレを覚えるまで仔犬の行動範囲を制限することも必要です。
※仔犬の行動範囲を制限することで、トイレも教えやすくなります。
▽あせらない▽
最初から決められた場所でトイレができる仔犬はいません。
もしもそんな仔犬の話を聞いたら、その飼い主さんは非常にラッキーな人なんだと思ってください。
普通はトイレを覚えるのには時間がかかりますし、人間にも失敗されないような工夫や努力が必要になります。
「どのくらいでトイレを覚えるのか」 という飼い主さんにとっての大問題は、千差万別。
2~3日で覚えてしまうコもいれば、数ヶ月を要するコもいます。
まさにケース・バイ・ケースですので、犬の飼い方の本の通りにいかなかったり、他の飼い主さん達の話を聞いて「どうしてウチのコはだめなんだろう」 と落胆しないでください。
▲ 仔犬のトイレパターン
まず仔犬の行動をよく観察してください。
オシッコやウンチをする前には、必ず何らかの兆候や行動があります。
急にソワソワし始めたり、その場のニオイをかぎ始める、一ヶ所でクルクル回り出すなどが一般的なトイレ前の行動です。
仔犬の行動をよく観察して、トイレのタイミングをつかむようにしましょう。
その他にも、犬 (特に仔犬) がトイレをするタイミングとしては、次のようなものがあります。
●食餌の後
●寝起き
●興奮した時 (留守番の後など)
仔犬は長時間トイレを我慢することはできません。
生後2ヶ月くらいなら、大体3~6時間の間隔で排泄します。
トイレを覚えるまでは、ある程度人間がつきっきりになる覚悟が必要です。
▲ トイレの場所
犬に限らず全ての動物にとって、排泄をする時は非常に無防備な状態になります。
そのため仔犬のトイレの場所は、部屋の隅やサークルの中などの落ち着ける場所が適しています。
特に神経質な性格のコでは、排泄するところを見られたくなくて物陰などでしてしまうことがあります。
トイレの場所は、仔犬が落ち着いてできるよう、工夫してあげましょう。
市販の犬用トイレやトイレシートがありますが、空き箱や新聞紙などで代用することもできます。
新聞紙などを使用する場合には、下にもれないように、一番下にビニールシートを敷くなどしてください。
また犬は自分の寝床を汚さないようにする習性がありますので、小型犬ならばサークル内の半分を寝床スペースにして、残った半分をトイレスペースにする方法もあります。
ただし、退屈してトイレシートで遊んでボロボロにしてしまうことがあるので、注意が必要です。
そして一度決めたトイレの場所は、できれば移動させない方が良いでしょう。
2.トイレの教え方
▲ 仔犬がトイレを覚えるまで
犬がいろいろなしつけを覚えるためには、『条件付け』というものが必要になります。
ある行動 (飼い主が望む行動) をすれば犬にとって嬉しいことがあり、ある行動(飼い主が望まない行動) をすればイヤなことがあるというやり方で、飼い主が望まない行動をさせないようにしていく方法です。
仔犬にトイレを覚えさせるには、まず 「人間の用意したトイレ=排泄する場所」ということを教える必要があります。
そのためには、決められた場所でトイレをした時にはほめられる(犬にとってのごほうび)、それ以外の場所でした時にはほめてもらえないどころか無視されてしまう(犬にとってはつらい罰)、という人間の態度によって教えます。
犬は人間の精神状態や行動をよく観察していますし、非常に敏感です。
大きな声を出して叱らなくても、自分が無視されたり、飼い主がうんざりしたようにおもらしの後始末をしていると、仔犬は非常に恐縮したような不安そうな表情を浮かべます。
※ このような精神状態の仔犬は、十分に罰を受けていますので、それ以上叱ったりしないでください。
「ごほうび」 と 「罰」 を、常に同じ条件で与えることを繰り返すことで、よりほめられたい仔犬は「罰」 を受ける行動を取らなくなり、ほめられる行動のみをするようになっていきます。
▲ 気付いたら、すぐに連れて行く
仔犬のトイレサインに気付いたら、すぐにトイレに連れて行きます。
ただし、あわてて大きな声を出したり、バタバタと走り寄って乱暴に抱き上げたりはしないでください。
仔犬が驚いておもらしをしてしまったり、逆に尿意や便意がなくなってしまうことがあります。
最初のうちは、トイレをした時間をメモしておくと、大体のトイレ間隔がつかみやすくなります。
トイレに連れて行ったら、仔犬がトイレをするまでそばについています。
ただし、早くトイレを覚えて欲しくて真剣になるあまり、じっと仔犬の目を見つめたりしてはいけません。
見られていることで緊張してしまい、排泄ができなくなってしまうコもいますので、なるべく仔犬から目線を離してあげましょう。
そしてトイレスペースできちんとできたら、すぐにほめてあげてください。
言葉でほめるのが苦手な人は、トイレから出した仔犬とボールなどで少しの間遊んであげるのも、効果的です。
十分に仔犬をほめてあげてから、トイレを掃除します。
(すぐに片付け始めると、仔犬が無視されたように感じることがあります)
最初のうちは、トイレシートや新聞紙などを交換する時に、新しいシートに少しオシッコのニオイをつけておくようにしましょう。
ニオイによってもトイレの場所を教えることができます。
▲ かけ声(合図)を決める
絶対に必要というわけではありませんが、教えておくと便利なことの1つです。
仔犬がトイレをする時に、決まった言葉 (『オシッコ』、『トイレ』など) をかけましょう。
排泄の時に常に同じ言葉をかけ続けることで、その言葉と排泄が条件付けされていき、「合図をしたらトイレをする」ということが可能になります。
同時に、合図が出されない場所で好き勝手にトイレをするということはなくなっていきます。
(去勢してないオス犬では難しいです)
これは、盲導犬や聴導犬などのサービス・ドッグの基本トレーニングの一つとして行われているトイレトレーニングです。
人間といろいろな場所に行くサービス・ドッグ達は、いつでもトイレをするというわけにはいきません。
そのため、トイレのできる時や場所に行くと、ユーザーが合図をしてトイレをさせます。
(『ワン・トゥー』 というかけ声が使われています)、
一般の犬でも、フリスビーなどのドッグ・スポーツに参加する時や旅行に連れて行く時、長時間の留守番をさせる前など、飼い主の都合に合わせてトイレをさせることができるので、教えておくと便利です。
3.トイレの場所を変える時
▲ 変更は少しずつ
トイレの場所を移動させる時は、いきなり変えないでください。
特に別の部屋や室外など、それまでしていた場所からまったく見えない場所に移す時には、少しずつ移動させていきます。
最初のうちは失敗することもあるかもしれませんが、叱らずにトイレトレーニングを最初からやり直すつもりで取り組んでください。
また、トイレの場所を変える時には、それまでトイレとして使っていた容器は変えてはいけません。
仔犬はトイレを場所だけでなく、その形によっても記憶しています。
場所と容器の両方を一度に変えてしまうと、仔犬がとまどって失敗する確率が高くなります。
一般的にトイレの場所の変更は、仔犬が完全に「トイレ=排泄の場所」 と覚えた後の方が、スムーズに行うことができます。
▲ 室内のトイレを室外に移す時
トイレを完全に家の外に出す時には、特に注意してください。
犬は勝手に家の外に出ることはできませんので、その分人間がきちんと家の外に連れ出してあげなくてはいけません。
生後半年を過ぎていれば、仔犬は約6時間ほどはトイレを我慢できますし、成犬ならば半日くらいは我慢することができます。
しかし、限界までトイレを我慢することを続けていると、膀胱炎を起こすことがあります。
成犬になってからも、1日に最低3回はトイレに連れ出すようにしてください。
飼い主の利便性を考えるなら、室内飼いの犬(特に小型犬) の場合、屋外だけでなく家の中でも排泄できるようにしておいた方が、雨の日に排泄のためだけに外に出す必要がなくなるので便利です。
4.ありがちな失敗
▲ 隠れた場所でするようになってしまった
特に臆病だったり神経質な性格の仔犬に対して、おもらしを叱った場合に起こりがちです。
おもらしをしている最中や直後に気付いて叱ってしまうと、仔犬は「トイレしたことを叱られた」 と感じてしまいます。
排泄すること自体を悪いことだと考えてしまうと、隠れた場所でするようになってしまいます。
いつもは叱らないように気をつけていても、ついついはずみで叱ってしまうこともあるでしょう。
その結果、仔犬が隠れてトイレをするようになってしまったら、気持ちを入れ替えて、もう一度トイレトレーニングをやり直していきましょう。
一度失敗をしたことで、仔犬が傷つきやすいことがわかっているので、2度目は仔犬の気持ちを考えてあげられると思います。
また、叱られたことで落ち込んでしまったり、隠れてトイレをするようになってしまう仔犬は、人間が好きでほめてもらいたいという欲求が強い傾向にあります。
人間が先回りして失敗しないような状況を作ってあげると、スムーズにトイレを覚えさせることができます。
(これは、全てのしつけに対して同じことが言えます)
▲ トイレに行く途中でもらしてしまう
これは、仔犬がトイレを覚えかけた頃に、よくやってしまう失敗です。
夢中になって遊んでいる時などに突然尿意に気付き、あわててトイレに走って行くのに、間に合わずに途中でもらしてしまうことがあります。
このような時、仔犬はきちんとトイレの場所を意識して、「オシッコはトイレでする」ということをわかっています。
トイレに対する意識をきちんと持っている状態での失敗ですので、決して叱らないでください。
特に仔犬がうなだれて耳を後ろに倒していたり、上目遣いに飼い主の顔を見上げたりしている時、仔犬は自分が失敗したことをハッキリと意識しています。
このような失敗をなくすためには、仔犬が興奮しすぎないように人間が注意する必要があります。
熱中して遊んでいる時でも、一緒に遊びながら時々「オスワリ」 などの簡単なトレーニングを入れるなどして、仔犬が冷静さを取り戻せる瞬間を作ってあげるようにすると良いでしょう。
▲ トイレでするけれど、はみ出してしまう
これも、トイレを覚えかけた頃によくある失敗です。
トイレに行って、前肢がトイレにかかった状態で「トイレに着いた」 と勘違いしてしまうために起こります。
これも、仔犬はきちんと意識してトイレに行っていますので、叱ってはいけません。
このような失敗を防ぐためには、仔犬がトイレに向かった時に一緒について行き、はみ出さないように仔犬をやさしく誘導してあげてください。
ただしオモチャやおやつを使うと、仔犬の注意がトイレからそれてしまいます。
トイレをはさんで仔犬の向かい側に座り、名前を呼んで誘導します。
またダックスフンドやコーギーなどの胴長の犬種の場合、どうしてもお尻がトイレからはみ出してしまいがちです。
犬の体の大きさをよく見て、そのコの体格に合ったサイズのトイレを使用するようにしましょう。
▲ 興奮しておもらししてしまう
留守番の後や来客があった時など、興奮してもらしてしまうことがあります。
特に甘えん坊だったり、人間が大好きな性格のコがよくやってしまう失敗で、成犬になってからも起こりがちです。
叱ってしまうと、犬にしてみれば留守番が終わった途端に叱られたり、来客があると叱られることになるので、留守番嫌い、来客嫌いになってしまう危険があります。
また、相手に対してお腹を見せておもらしをするのは、犬にとっては最大限の服従の表明ですので、絶対に叱ってはいけません。
犬にしてみれば 「これ以上はない服従を示したのに叱られた」と感じてしいじけたり、最悪の場合、人間不信になることがあります。
このようなおもらし癖に対しては、なるべく興奮させないように注意しましょう。
まず、どんな時に興奮しておもらしをするか、その時に自分がどんな態度で犬に接しているか、よく考えてみてください。
帰宅した時に 「留守番させて寂しい思いをさせた」と大げさに名前を呼んだり、いつもより熱烈に犬をかまっていませんか?
気持ちはわかりますが、犬の興奮をあおることになり、おもらしを直すためには逆効果です。
留守番させた後に必ずおもらししてしまうコには、帰宅した時には冷静に「ただいま」 と声をかけるくらいにしましょう。
同時に、家を出る時にも大げさに犬をかまったりせず、冷静に犬と接するようにします。
要は 「留守番は何でもないこと」 で、「飼い主の帰宅は嬉しいことではあるけれども、必ず帰ってきてくれるのだから、そんなに興奮することはない」と認識させるわけです。
最初は、急に飼い主の態度が変わったことで犬がとまどうかもしれません。
ですが徐々に慣れていきますので、飼い主も気持ちを抑えて犬の出迎えを受けるようにしてください。
留守番中にトイレを我慢してしまうコや、サークルの中に入れて留守番をさせている場合は、まずトイレをさせた後で遊んであげると良いでしょう。
来客に対して興奮しておもらしする場合も同様です。
最初は知り合いに協力してもらって来客役になってもらい、冷静に犬に接してもらうことで、来客がそれほど興奮する必要のないものであることを教えます。
その場合、犬の行動をよく見て、興奮がつのってきたら、一度「オスワリ」 をさせるなどしてみてください。
犬の気持ちをそらすことができれば、おもらしを防ぐことができます。
興奮してのおもらしである 「うれション」 は、飼い主も犬の喜びようがわかる上に、自分の帰宅をそれ程喜んでくれるのかと悪い気はしませんから、他のトイレの失敗に比べると直すのが難しいものです。
しかし、途中で情に負けてトレーニングにくじけてしまうと、逆におもらし癖を強化してしまいます。
うれション癖を直すためには、ある程度心を鬼にする必要があると覚悟してください。
5.すぐに覚えられるコ・覚えられないコ
▲ 犬種の特徴
犬種によって、トイレを覚えるのに早い・遅いの傾向があります。
一般的に人間との結びつきを強く求める犬種や頭がよいとされる犬種は、トイレを覚えるのも早いようです。
逆に孤独を好む傾向の強い犬種や好奇心が旺盛すぎる犬種は、トイレを覚えるまでに時間がかかることが多いようです。
ですが、トイレを覚えるのに時間がかかる犬種でも、辛抱強く教えていれば必ず覚えさせることはできます。
逆にそのような犬種は完全に覚えさせることさえ出来れば、以後は頑固なまでに自分の覚えたことを守り通す癖があります。
またオスとメスではメスの方がトイレを覚えるのが早いようです。
▽トイレを覚えるのが早い犬種▽
ボーダー・コリーやシェルティーなどの牧羊犬種
リトリーバー種
ジャーマン・シェパード
プードル
パピヨン
コッカー・スパニエルなど
▽トイレを覚えるのに時間を要する犬種▽
アフガン・ハウンドやボルゾイなどのサイト・ハウンド種
テリア種(エアデール・テリアは除く)
チャウチャウ
シー・ズーなど
▲ 性格による違い
トイレに限らず全てのしつけにおいて、従順な性格の犬ほど覚えが早く、独立心の強い犬ほど覚えるのには時間がかかります。
ただし、独立心旺盛な性格の犬が頭が悪い・覚えが悪いというわけではありません。
飼い主が自分のことをどう思おうと気にしていないので、人間が求める行動をなかなか覚えないわけです。
このような性格の犬にとって、飼い主に叱られることは罰ではなく、飼い主からの敵意と受け止めてしまいがちなので、むやみに叱るのは禁物です。
失敗しない状況を人間が作ることで、少しずつ教えていくようにしてください。
またやんちゃな性格の犬の場合、自分がおもらしをした後に、飼い主があわてる姿を見て面白がり、わざとトイレ以外の場所でするようになってしまうことがあります。
犬が期待しているようなあわてた行動はせず、犬を無視して冷静に後片付けをしましょう。
逆にきちんとトイレをした時にはたっぷりとほめ、お気に入りのオモチャで遊んであげるなどすると効果的です。
分離不安を特捜せよ!~ペットを不安にさせないテクニックとは?
はじめに
米国のヒット映画Home Alone(「ホーム・アローン」1992年)は家に置いてきぼりにされた大家族の末っ子が、たった一人で泥棒を撃退するというコメディ映画です。
犬もたった一人で留守番をする機会は少なくないですが、“ホームアローン(ここではペットが家に残されて家族全員が出かけてしまった状況の意味)”となった時に物を壊したり、過剰に吠えたり、トイレ以外の場所でオシッコをして困った経験はありませんか?
分離不安症とは?
最近では飼い主のペットに対する意識向上と共に“家族“として屋内で飼育される犬や猫が増えて来ました。家族の愛情に包まれて生活することはペットにとって幸せである一方、独りになる時間が少ないペットは、留守番をしなければならなくなった時に上記のような問題を起こすことがあります。
本来犬は社会性の強い動物であり、特に母犬や他の犬達と一緒に過ごしてきた犬達にとって独りきりで留守番することに慣れていないため、留守番中に不安が強くなります。飼い主が一緒にいる時には全く問題がないにも関わらず独りになると不安を感じ上記のような行動をとることを獣医学領域では「分離不安症(Separation anxiety )」と呼ぶ。分離不安は犬の問題行動における最も一般的な原因の一つなのです。
同じような問題はヒトの乳児でもみられます。親が自分から離れるともう戻ってこないのではないかと不安を感じ、単に隣の部屋に行っただけでもパニックを起こして泣くのです。
分離不安症はどんな犬に起こりやすいのか?
早期に離乳することや単独飼育は分離不安症のリスクファクターではなく、飼い主の過剰な接触あるいは過剰な愛情(Hyperattachment)が分離不安症と関連があります。
また飼い主と毎日1対1で密着した生活を送っている犬は、複数の家族と共に生活している犬よりも約2.5倍分離不安症になりやすいと言われています。社会性動物として、子犬が母犬や兄弟への愛着を形成することは正常なことで、子犬が家族といったん切り離されると通常は人間との新しい生活を構築し、その環境にアジャストするのですが、飼い主にひどく依存する傾向がある犬では分離不安症となります。
若い頃のトラウマ的な出来事を経験した犬も分離不安症となる可能性が高いと言われています。また愛情の喪失(ペットショップに長い間いることやアニマルシェルターでの長い生活)・突然の環境変化(新居への移転)・飼い主のライフスタイルの突然の変化・家族メンバーとの長期的あるいは一生の別れ(離婚、新生児の誕生、死別)・新しいメンバーの追加(子供、ペット)などもリスクファクターと言われています。
分離不安症になるとどんな症状がでるのか?
飼い主がいる時は穏やかでも、いったん飼い主が外出して犬だけで留守番をさせた場合に犬が過度の不安を感じ問題行動を起こす。
飼い主が外出の準備を始めた段階からドキドキしたり落ち着かず飼い主の後をつきまとうなどの分離不安症の“前兆”が始まり、破壊行動は通常外出後数分で始まる。タフツ大学獣医学部の行動薬理学教授のニコラス・ドッドマンは最初の30分が最も重要である言う。
過剰に吠えたり、リビングやベットなどトイレ以外の不適切な場所での排便や排尿をすることもある。
犬は快適でもグルーミングをするが、分離不安症の稀なサインとして自分の足をペロペロ舐めて皮膚が赤くなる(肢端舐性皮膚炎)こともあります。不安という“ストレス”が原因の皮膚炎は通常大型犬に見られ強迫神経症の一形態と考えられています。
長時間独りにされたり制限された状況や緊張が多い環境に置かれつづけることによって引き起こされる欲求不満や不安の“SOS”なのかもしれません。
猫でも分離不安症を起こしえると考えられていますが、犬と違って最も多いサインは「不適切な場所での排尿」と言われています。この場合ほとんどが飼い主のベットにするのが多く、決して飼い主への“報復”ではありません。
自分の犬が分離不安であるか知る方法とは?
以下の全てあるいはほとんど当てはまる場合は分離不安症の可能性が高い。
①独りになった時に問題行動が強く現れる。
②家にいるとあなたの後ろをついてまわる。
③帰宅した時に大袈裟に感情を表現する。
④犬が独りになると飼い主の留守の時間に関わらず必ず症状が出る。
⑤あなたが外出する準備を始めると興奮し、不安になり、落ち込む。
⑥犬が独りで野外で過ごすことが好きではない。
分離不安症の一歩手前の症状とは?
潜在的な分離不安症、つまりサッカーで例えると「レッドカード」の一歩手前である「イエローカード」となる症状は
①飼い主につきまとい、何とか飼い主の関心をひこうとする。
②飼い主が出かける準備を始めると、不安状態を示す。
③飼い主の帰宅時に、過剰に喜んで出迎える
分離不安の犬に対する戦略とは?
最も効果的なアプローチは行動療法と薬物療法の組み合わせと言われています。
行動療法は飼い主の外出/帰宅時における犬のパニックレベルを減少させることにピントを合わせます。
外出前に犬を興奮させたり、「いい子で待っててね」などの声をかけて外出することは精神的な落胆が大きく不安感を助長させます。従って一般的には外出前約30分はあまり犬を興奮させるような遊びをしないように注意します。帰宅後も犬が大喜びで尻尾をブルンブルンまわして興奮している間は一切関心を向けないようにします。「いい子にしてたのね、ごめんね」などと声をかけ頭を撫でることもやめ、さらには視線も合わせず無視することが効果的と言われています。愛犬家にとっては非常に受け入れがたい作戦ですが、非常に重要なことです。
また帰宅後に破壊行動や不適切な排泄を叱り付けてはいけないと言われています。犬は数秒以上経過した過去の過ちを怒られても理解することは不可能で、逆に犬の不安感を高めることに繋がります。
分離不安を伴う犬に最も効果的な戦略は非常に短い期間から“ホームアローン”に慣れさせることです。
ステップ1:外出の準備をしてソファーに座る。
ステップ2:外出の準備をして鍵を持ってドアを開けるだけで戻る。
ステップ3:外出の準備をしてドアを開けて閉めないで見えなくなる。
ステップ4:外出の準備をしてドアを閉じて数秒後に直ぐ戻る。
ステップ5:外出の準備をしてドアを閉じて数分後に戻る。
このように少しずつサインがなくなるまで時間を少しずつ長くして慣れさせる。同時に、“ホームアローン”が楽しいことだと犬に関連付けなければなりません。例えば出掛ける前におやつをいくつかの場所において、犬にばれないように裏のドアからこっそりとでかけることはナイスアイデアでしょう。
「安心の方程式」を確立することも役に立ちます。通常、犬は飼い主の「短時間の外出」にある手がかりを関連付けて学びます。例えば、テレビやラジオが付いたままであればゴミを捨てに行くかコンビニに弁当を買いに行くだけで直ぐに戻ってくることを知っているので不安になりません。つまり犬にとって「テレビやラジオの音が付いている」は「安心の方程式」なのです。しかし音が全て消えて鍵を持った場合はしばらく帰宅しないと学習しています。従って「長時間の外出」に「安心の方程式」を関連付けることは役に立ちます。破壊行動が重度の場合は「安心の方程式」としてコングや飲み込む危険性の少ないおもちゃを与える、あるいはTシャツなどあなたのにおいのついた衣服を犬に与えて外出することはグッドアイデアです。
より重度の分離不安の犬に対する感情抑制テクニックとは?
飼い主が外出前にする行動(例えば化粧をしたり着替えたり、鍵やカバンを持つなど)をとると、独りぼっちになってしまうと不安に陥ります。従って犬にとっては例えば「化粧=不安」という「寂しさの方程式」が成立してしまいます。そこで、化粧をして出掛ける振りをしながらのフェイントで外出しなかったり、車の鍵をもって実はトイレに行くだけにして「寂しさの方程式」を崩すことが大切となります。自動販売機で「コーラ」のボタンを押すと必ず「コーラ」が出てくることを数学的には1対1対応と言います。分離不安の場合「コーラ」のボタンを押しても「カルピス」がでてくるかもしれないことを犬に教えることが大切となるのではないでしょうか・・・
行動療法を開始する場合、家族全員の協力が必要となります。奥様だけが勝手に上記の作戦を決行すると「うちの妻は頭がおかしくなったか?」と旦那様に誤解されますので家族の中で分離不安の戦略について“温度差”がないようにしなければなりません。
重症の場合は行動療法に加え、精神安定剤も併用する作戦が効果的です。
脳内の神経伝達物質である「セロトニン」は孤独感やうつ状態を緩和する物質と理解します。
つまり「セロトニン」が不足すると感情にブレーキがかかりにくく“うつ状態”となります。実際、分離不安症を呈する犬では、不安に関与するセロトニンの脳内での作用が弱い傾向にあると言われています。そこでヒトの精神科医でも過食症やパニック障害の治療に処方されている三環系抗うつ薬(塩酸クロミプラミン:ノバルティス社)が犬の分離不安症の治療補助剤として一般的に使用されています。この薬は抗うつ薬の中でもセロトニンの量を増やす作用が強いことが特徴で、飲むことによって間接的に脳内のセロトニンの作用を高め、不安をやわらげると考えられています。
まとめ
分離不安は飼い主とペットとの強すぎる絆が大きく影響しているようです。いくつかの問題行動は飼い主への嫌がらせや復讐ではなくパニックによる反応であることを理解することが大切となります。分離不安に関して完全に理解されているわけではありませんが、分離不安は非常に身近な問題です。あなたの犬は冒頭で述べたような極端な行動を示さないかもしれませんが、時々食べない、飲まない、吐く、下痢をするといった症状は「ホームアローン」が影響しているかもしれません・・・
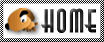
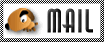
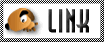


 質問は・・・
質問は・・・