犬の病気早期発見チェックリスト
犬は、人間のように「痛い」などの自覚症状を言葉にして伝える事ができません。
犬をはじめ動物は、本当は体調が悪くても本能的に隠そうとするのだそうです。
そのため明らかな異常に気づいたときには深刻な状態になっていることも。
ですから日頃から愛犬の健康状態をよく観察して、ふだんと違うところはないか、微妙な変化を感じとり、病気のシグナルをできるだけ早期に発見してあげなければと思います。
幼犬のころから、体のどこを触られても嫌がらないようにたくさんさわって慣らしておくと、日常の愛犬のお手入れ時や動物病院での検査や治療に役にたちます。
気になることがあったら、なるべく早く動物病院へ相談してください。緊急時などのことも考えて、夜間も診てもらえる動物病院や信頼できる動物病院をきちんとさがしておくことも大切です。
《 犬の体をチェック 》
まずは愛犬の健康時の状態を知っておくことがまず第一です。そうでないと、異常に気づくことができません。
● 食欲は?
食欲はおちていませんか?食欲の有無は、健康状態のバロメーターです。ただし、愛犬の好き嫌いや、運動量や年齢・季節、あたえる環境の変化などによっても左右されます。またあたえるフードの管理は大切です。
フードが酸化してしまっている可能性も。
急に食欲がおちたり、逆に食欲がありすぎるのには注意が必要です。
中年以降の犬は、糖尿病や副腎の病気で食欲が異常におこることがあります。
● 体重は?
体重管理はとても大切です。肥満は人間どうよう、糖尿病などのいろいろな病気の引き金になります。
また、ヘルニアなどの骨格系のトラブルにつながる可能性もあります。
やせてくる場合。よく食べるのにやせてきたりしていませんか?犬がやせてきたとき、最初に疑われる病気は心臓病です。また、子犬の体重減少も危険です。新生犬の体重が3日ふえない、減少する場合、命にかかわる危険性があります。
<愛犬の体重は、家庭ではかることができます>
あらかじめ、飼い主さんの体重をチェックしておきます。そして、愛犬と飼い主さんが一緒に体重をはかります。
その体重から、飼い主さんの体重をさしひけば愛犬の体重がわかります。
● うんちの様子は?
ゆるくありませんか?(うんちがやわらかい)下痢をしていませんか?血が混じっていませんか?
うんちがでないことはありませんか?(便秘)うんちの異常の30%は要注意といわれています。
フードを変えたり、食べすぎたり、環境やストレスなどによってもゆるくなったりします。
寄生虫や細菌感染、伝染病、中毒などによっても下痢したり、血便がでたりすることがあります。
下痢をしている時でも、元気がある場合はさほど心配ありませんが、元気がない場合や食欲が落ちてる場合は要注意。
犬の便秘は少ないですが、あります。あたえるフードの量がすくない時や、カルシウム過多のフードを与えている・前立腺肥大により排泄しにくい場合があります。
気になるウンチは、動物病院へもっていき検査してもらいましょう。
● 尿のようすは?
尿の色がおかしくありませんか?尿がでないとか、異常に少ないことはありませんか?ニオイがきつかったりしませんか?
まず第一に、愛犬が健康なときのおしっこの状態を知っておくことが大切です。
尿の色がピンク色や赤い場合、腎臓や尿路系の異常が考えられます。尿の色が黄色が濃いのは、水分不足が考えられます。
飲水量の不足は脱水、膀胱炎など泌尿器系の病気の原因になります。
尿のニオイがきつかったり色がにごっている場合、尿路の炎症がおきており、膀胱炎のことが多い。
尿がキラキラ光る場合、膀胱炎の可能性があり結晶がまじっていることがあります。
放置していると尿路結石になったり、尿道閉鎖に進行することも。
極端に尿量が少ないとか、尿が出ない場合、膀胱炎や前立腺の病気・尿路結石・腎不全などの病気が考えられます。
気になる尿は、なるべく新しい尿を栓つきの清潔な瓶などに入れてすぐに動物病院へもっていき検査をうけましょう。
● 元気がありますか?
健康な子犬は活発で動きまわるものです。ぐったりしていませんか?
眼にちからがなくトロンとしていたり、動きたがらないかったり無関心ではありませんか?
高齢犬だから動きたがらないのだと決めつけないようにしましょう。慢性の関節炎もちの高齢犬が散歩のあと2~3日元気がなくなったりすることがあります。心臓病や腹部に腫瘍があるとき、周期的に元気がなくなるなどの場合があります。
犬は、体調がわるくても飼い主の前では本能的にそれを隠そうとするものです。急に元気がなくなったり、ずっとだるそうにしているなど、目で見てあきらかに元気がない場合、なんらかの異常がおきている可能性が高いのですぐに動物病院へ。
●耳は?
耳をかゆがってかいたり、頭をつよくふったりしていませんか?
耳のなかが臭くありませんか?耳の中が汚れていませんか?茶褐色や黒っぽい汚れなどがありませんか?
耳そうじをしてあげても、すぐに汚れてくることはありませんか?耳が腫れてきていませんか?
耳のたれさがっている犬種や耳の中に毛が多く生えている犬種はは外耳炎になりやすく、外耳炎にかかるとかゆみや痛みをともなうため、犬は頭をふったりかいたりします。
外耳炎は、細菌や真菌(カビ)、アレルギー、耳ダニなどの原因によりなります。
中耳炎や内耳炎にかかると、膿がでて悪臭がします。
内耳がおかされると、運動障害やしゃけいなどの症状がでます。最終的に死亡することも。
急に耳の中が厚くなり穴がみえなくなる位腫れてくる場合、ノミや食物アレルギー・アトピーなどによる原因が疑われます。
耳の異常はとても不快なので、頭をつよくふったり耳をひっかいてしまったりして、耳介が腫れあがってしまったりすることもあります。ストレスをためないためにも、すぐに動物病院へつれていってあげましょう。
<耳垢のカンタンな見分け方>
*黒い耳垢や膿 … 中耳・外耳炎の悪化
*茶褐色 … 耳ダニ・マラセチア外耳炎など
● 眼は?
眼の輝きがありますか?白目が赤くなっていませんか?かゆがったりしていませんか?角膜が白くなっていませんか?目ヤニや涙がよくでませんか?逆に目が乾いていませんか?まぶたが震えていたり、まぶしそうにしていませんか?
もっとも多い目の病気としてあげられるのが結膜炎で、涙や目ヤニが出て、充血したりかゆみや痛みをともないます。いつも涙がでている場合、さかまつげや涙管閉塞のことが多いようです。
角膜が白くみえる場合、白内障を疑います。早期に発見できれば治療は可能ですが、薬で白内障を治すことはできません。一般的には、発症して半年いないであれば手術はかなり有効のようです。
緑内障は、眼の色が緑色から赤色にみえたり、目が痛いために目をつぶることが多くなります。眼全体がふくらんできたりします。早期に治療しないと、急性の場合2~3日で視力を失います。目の輝きがなく、くもってみえる場合、視力をうしなっている可能性があります。
犬は嗅覚がすぐれているので、人間ほど視力に頼っていません。
たとえ失明していても、慣れている場所ではぶつかったり不自然な動作をすることも少なかったりして、飼い主さんが犬の失明にしばらく気づかないこともあるようです。ふだんからよくチェックしてあげて、すこしでも異常がみつかったらすぐに動物病院へつれていってあげましょう。
● 鼻は?
鼻は湿っていますか?乾いていますか?くしゃみや鼻水がでていませんか?膿のような鼻水ではありませんか?鼻血がでていませんか?
犬は起きているときは鼻が湿っていて、眠っているときや起きたすぐあとでは鼻が乾いています。
水のような鼻汁がタラタラでていたり膿のような鼻汁がでる場合、細菌やウイルスの感染・アレルギーなど原因が多くあります。
ほうっておくと、副鼻腔炎などを続発して鼻ずまりがひどくなり呼吸困難になることもありますので、すぐに動物病院で治療をうけてください。
● お口は?
口臭がひどくありませんか?よだれがでたり、口を閉じないことはありませんか?口や歯茎から出血していませんか?歯が折れたり、かけたり、抜けたりしていませんか?食べたそうにしているのに食べないことはありませんか?口の中が黄色い、または白くなっていたりしませんか?歯が二重にはえたりしていませんか?
犬の口が臭いとき、原因の多くは歯石や歯周病にあります。
口内炎になると、口臭・口の痛み・食欲不振・よだれなどの症状がでます。内蔵疾患や、鼻の病気・寄生虫でも口臭がでます。
よだれは乗り物酔いや中毒・てんかんなどのほか、口のなかをケガしていたり体のどこかが痛い場合もあります。
犬の歯肉や舌の色は濃いピンク色かすこし赤みがかっているのが正常です。黄色い場合、内臓疾患の疑いが。白っぽい場合、体が冷えているもしくは体温が低下している危険信号です。
犬の歯がかけたり、折れたり、抜けたあと、ほうっておくと、そこから細菌が侵入し、体全体へまわり臓器の機能障害をおこすこともあります。
生後10ヶ月くらいまでに、永久歯に生え変わりますが、まれに乳歯(とくに犬歯が多い)が残ったまま2重に生えたりして、永久歯が正常に生えなくなる場合があります。口臭の原因にもなります。しばらく様子をみて抜けないようなら、抜歯の必要があります。
人間とおなじで、犬も歯はいのち!食べることは犬にとって大好きな欲求であり、生きるために必要です。すこしでもおかしいなと思ったら、動物病院へつれていってあげましょう。
● のどは?
のどにしこりがありませんか?せきをよくしていませんか?のどにさわるとすぐにせきがでたりしませんか?呼吸が速くありませんか?
咳が出たり呼吸が荒くなる原因には、気管の病気や心臓の異常・肺炎気管支炎・ケンネルコフなどいろいろ考えられます。
運動後にせきこんだり、夜中のせきがある場合、心臓病の可能性がたかく、運動は禁物で、安静をたもつ必要があります。一般的に弱々しいせきのほうが、重症なことが多いようです。
のどに腫瘍ができた場合、食べ物を飲み込めなくなったりして吐き戻したり、呼吸困難になったりします。
● 歩きかたは?
歩くのがつらそうではないですか?大好きなはずなのに、散歩にいきたがらないことはありませんか?
いつもと歩き方が違うことはないですか?
犬がふつうに歩けずに足をうかせていたり、ひきずっていたりする場合、どこかが痛いからです。つめが伸びすぎていたり足裏にトゲがささっていたり、ケガや脱臼の可能性があります。
また、足の付根や肩・股関節などの筋肉や骨に異常がおきているのかもしれません。フラフラ・ヨタヨタしているときには、さらに神経麻痺の可能性もあります。無理をさせないで、すぐに動物病院へ。
● おなかは?
おなかがふくらんでいませんか?乳房にしこりがありませんか?さわると痛がったりしませんか?
おなかの一部分や乳房などにしこりがある場合、腫瘍の可能性があります。高齢になると乳腺に腫瘍ができやすいので、1ヶ月に1度乳がんのチェックが大切です。
おなかがふくれてくる場合、メス犬なら妊娠の可能性や、フィラリア症などにより腹水がたまっている可能性もあります。
腫瘍は命にかかわる可能性が高いので、普段から愛犬とスキンシップをとってしこりなど手にさわるものがないかチェックしてあげましょう。気になることがあったら、早めに動物病院へ。
● 皮膚は?
かゆがっていたり、フケが多くでたりしてませんか?一部分だけ脱毛したりしていませんか?皮膚が赤くなったり、ただれたりしていませんか?
犬がかゆがる動作は、なめる、かむ、すう、引っかくです。
かゆがる原因はいろいろ考えられ、アレルギーや寄生虫感染、細菌感染、カビによる感染、ダニやノミによるもの、ストレス、食事をかえた場合などがあります。激しいかゆみをともなう疥癬(かいせん)は、人にもうつります。
脱毛には、かゆくてかきむしったり、皮膚炎により毛自体が弱くなったり切れたりすることのほか、接触性アレルギーや、ホルモンバランス異常によるものなどがあります。
皮膚病の原因の特定はとても複雑でむずかしいので、いつからかゆがりはじめたのか、どの季節にかゆがるか、どの程度かゆがるか、どこが一番かゆがるのかなど、よく観察して原因の特定につとめ、治療や診断に役立てましょう。カユカユは愛犬にとってとてもストレスになります。
はやめに動物病院へいって相談、治療を開始しましょう。
● おしり・肛門周辺は?
お尻を床にこすりつけたりしていませんか?お尻をなめたり、気にする様子は?お尻が赤くはれたりしていませんか?
肛門膿(こうもんのう)がたまっていると、ムズムズしたりして不快なので、犬は前足だけをつかって前進し、床にズリズリこすりつけたりします。寄生虫がいる可能性もあります。
肛門のまわりがはれている場合、肛門膿炎や肛門周辺の皮膚病の疑いがあります。
肛門膿がたまっている場合は、シャンプー時などにしぼってあげましょう。肛門膿はたまりやすい子とそうでない子があるようですが、比較的に小型犬に多いようです。肛門膿は動物病院でもしぼってもらえます。
犬の誤飲と応急処置
犬の誤飲事故はとても多く、飲みこんだものによって処置がちがってきます。
何かを誤飲してしまった後、いくら元気であっても安心はできません。
急に容態が悪くなってしまうこともあり、なかには命にかかわることも少なくありません。
愛犬の行動範囲内に、口にしそうなものや飲みこむと危険なものは置かないようにするのはもちろんのこと、誤飲してしまいそうなものがないか・落ちていないか・何かなくなっているものがないか日頃からチェックするようにしましょう。
まさかこんなものは飲み込まないだろうなんて軽く考えないで!
おもちゃなどで遊ばせる場合も、そのまま与えっぱなしにするのではなく、飼い主さんが一緒に遊んであげるか、しっかり見ていてあげてください。
ぬいぐるみの目や鼻といった部分が遊んでいるうちに取れて誤飲してしまうことも多いです。
とくに子犬のうちは好奇心が旺盛なので、なんでもすぐに口に入れようとしますから、注意しましょう。
無理に取り上げようとすると、あわてて飲み込んでしまう事が多いので、犬が飲み込めそうな物で遊んでいるときにそれを取り上げる時は、何かに気をそらせたすきに取り上げるようにしましょう。
万一、誤飲してしまったときは、できればすぐに動物病院に連絡して、指示を仰ぎましょう。
《 犬が異物を誤飲してしまった 》
家の中はとくに誤飲してしまいそうなものがいっぱい!
気をつけていても知らないうちに床に落としてしまっていたりすることもあります。
新聞紙といった紙類をビリビリにしたり、ぬいぐるみを噛みちぎり中綿を出すといった破壊行動が楽しい子は多いみたいです。
ぬいぐるみの中綿が少量うんちと一緒に混ざってでてきて誤飲が発覚したことがあります。
目や鼻につかわれているボタンもとれかけていて誤飲しそうになったこともあります。
どんな誤飲も安易に考えず、のどや胃、腸でつまってしまったり、最悪の場合命にかかわることもあるということをよく念頭にいれておかなければいけません。
犬にあたえるおもちゃは犬専用の危険のないものをえらんであげましょう。
<よくある誤飲>
● ヘアーゴム・輪ゴム・クリップなどの小物
消化されずに胃に残ったままになったり、先がとがっているものは内蔵を傷つけてしまう可能性も。
● ティッシュペーパー・紙類(トイレシートも含む)
少量ならうんちと一緒に排泄されるのでさほど心配する必要はありませんが、一度に大量に食べてしまったり、日常的に食べていると腸閉塞になることも。トイレシートの場合はお腹の中で膨張するので要注意!
● 糸や毛糸・ひも状のもの
ある程度の長さがあるひも状の物は腸に詰まって腸閉塞を起こしたり、ひっかかって内臓を傷つけてしまうこともあり危険です。無理に吐かせようとせずに動物病院へ。
● タバコ
タバコを食べてしまったり、灰皿の吸い殻の水などを飲むと中毒を起こします。
● ラップやビニール袋など
食べ物をつつんでいたラップなどはおいしいニオイがして誤飲してしまうことがあります。ビニールのシャカシャカ音って楽しいみたいで、遊んでいるうちに破って飲み込んでしまうことも。腸に詰まったり、遊びかたによって窒息する恐れもあり
● 鶏の骨や焼き鳥などのくし
鶏のからあげの骨など加熱された鶏の骨は、噛むと細く裂けてしまうため先がとがっており、飲み込んだ時に食道や胃腸を傷つけてしまうので危険です。
また、おいしいニオイがついた焼き鳥などのくしにも注意。のどや内臓に刺さったりして危険です。無理に吐かせたり取ろうとしたりせずに、早急に動物病院へ。
● ボール・ぬいぐるみなどのおもちゃ
犬にあたえるおもちゃ類は、できるだけ犬専用の危険のないものを選びましょう。ボールは飲み込んでしまわない大きさのものを選びましょう。開腹手術が必要になるケースも少なくありません。ぬいぐるみや人形の目・鼻・口に使われている事が多いボタンなどのパーツを食いちぎって飲み込んでしまうことも。また、破壊して中綿や詰め物を食べてしまうことも。
● 電池・磁石など
電池は内臓壁などにはりついてしまったり、中の化学物質が漏れてやけどのような症状をおこす危険があります。 また2つ以上の磁石や金属を一緒に飲みこむと、それらがひきあい腸壁をはさんではりついてあなをあけてしまうなど重篤な症状をひきおこす危険性があるため、急いで動物病院へ。
● 殺虫剤・除草剤・薬品・化粧品など
誤飲すると中毒を起こす可能性が高く最悪の場合、命にかかわります。吐かせないでかならず獣医師と連絡をとり、指示にしたがってください。飲んでしまった化学薬品により、処置がちがってきます。何を飲んだのかわかっている場合やその可能性があるものは、その容器ごと持参しましょう。その後の処置や治療に役立ちます。
除草剤は道端に生えている雑草などにまかれている可能性があります。また、殺虫剤は犬のそばで不用意にまかないようにしましょう。
● 洗剤・漂白剤
洗剤や漂白剤などの化学薬品などの毒物を飲んでしまった場合は、吐き出させてはいけません。かならず獣医師と連絡をとり、指示にしたがってください。飲んでしまった化学薬品により、処置がちがってきます。何を飲んだのかわかっている場合やその可能性があるものは、その容器ごと持参しましょう。その後の処置や治療に役立ちます。何を飲んだのかわからずに、泡をふく、おう吐、ひきつけなどの症状がある場合はもちろんですが、すこしでも誤飲した可能性があるなら、急いで動物病院へ連絡しましょう。おう吐や下痢、最悪の場合命にかかわります。
《 異物を吐き出させる方法 》
まずはじめにお願いです。
愛犬が誤飲してしまった時、飼い主さんは気が動転してしまいます。
すぐに吐かせたいと思うのは当たり前のことですが、吐かせてよいものと悪いものがあります。
飲み込んだそのときの状況により変わってきます。
決して無理に吐かせようとせずに、なるだけすぐに病院に連絡をして獣医師の指示に従ってください。
以下に吐かせるための緊急手当てを示しますが、あくまでも緊急時の対応ですのでまずは必ず獣医師の指示を仰いでください。
いつ、どれくらい、何を飲みこんだのか?がとても重要です。
比較的ちいさく丸いものは吐かせても大丈夫ですが、とがった部分のあるものや化学薬品は、無理に吐かせると逆に食道などをキズつけてしまう恐れがあります。
比較的小さな物の誤飲で、飲みこんでからそれほどたっていないのであれば、食塩や飽和食塩水・オキシドールなどを投与して吐かせることができる場合があります。
*飽和食塩水とは、水に食塩を溶かしてもうこれ以上溶けない状態になった食塩水のことです。
体重4~5kgの愛犬には食塩ならティースプーン1杯ほど、飽和食塩水なら8~10mlほど、オキシドールなら2倍ほどに薄めてティースプーン1杯ほど、犬の口に入れて飲ませます。
しかし、異物が腸まで達している場合はこの方法ではむずかしいようです。
飲み込んだかどうか曖昧な時や、飲み込んでしまった異物を吐き出させることができない場合は、病院でレントゲンによる異物の確認をし、場合によっては開腹手術が必要になることもあります。
しかし、飲み込んでしまった異物の大きさや形状によりますが、切開せずに内視鏡でとりだすこともできるようです。
犬のアレルギー
最近、アレルギー?と思われる症状がでる犬たちが多いようです。
涙がでる、痒がる、足の裏をなめる、換毛期でないのに毛が抜ける、フケ、ブツブツができる…など、いろいろな症状があります。
しかし、これらすべてがアレルギーと決めつけられるものではありません。
愛犬の生活環境を見直してみましょう。
フードやお水はいつも新鮮なものですか?
お水をあまり飲まないなどということはありませんか?お散歩はサボらずに行っていますか?
留守番ばかり、叱ってばかりなんてことはありませんか?
退屈しのぎやストレスによって足の裏などをなめてばかりいるこも少なくありません。
《 犬のアレルギーの原因 》
アレルギーにもいろいろな原因(アレルゲン)があり先天的なものもありますが、食事によるものが大きいと考えています。
その食事の主流となっているのはドッグフード。
残念ながら、一部の市販ドッグフードにふくまれる原料・添加物などが原因となり、アレルギー症状をひきおこしている場合もあるようです。
その次に、お水。
水分不足による老廃物の排泄不良が原因でトラブルが起きている可能性も高いようです。
その他の直接的な原因として、ノミアレルギー・アトピー・食物アレルギー・接触性アレルギー・
その他細菌性のもの、草、花粉、腸内寄生虫、ホルモン性、新建材の接触によるものなどがあります。
また、愛犬のシャンプーに含まれる合成界面活性剤や添加物も原因のひとつではないかと
危険性が指摘されています。
直接的な原因によるアレルギーは、基本的に原因となるアレルゲンを特定し、それを取り除くことができれば症状を軽くしたり、またはアレルギーの発症を防ぐ事ができます。
ですからまず第一に愛犬の生活環境を見直してみて、何が原因となっていそうなのか考えることが大切です。
犬のアトピー性皮膚炎
アトピーとはギリシャ語の奇妙な事(atopia)からきているといわれており、人間のアトピー性皮膚炎と同様、そのアレルゲンとなる原因物質は多岐にわたります。
けしてアトピーというアレルゲンがあるわけではありません。とくに問題となるアレルゲンはハウスダストマイト(イエダニ)で、その他花粉、ホコリ、フケ、カビなどを吸引する環境にいること、またストレスなどが複合されて症状が悪化してしますケースが少なくくありません。
主な症状はかゆみで、耳や目のまわり、わきの下、後肢の内側、指の間などに強い皮膚炎が見られます。いつも痒がったりしていませんか?年間を通して症状が見られる場合、ハウスダストや食物の原因かもしれません。
また、他に併発している病気があると治りにくく、あわせた治療が必要です。
《 生活環境を見直す 》
犬のアトピー性皮膚炎は人同様アレルゲンの特定が難しく、また遺伝的要素や体質による場合も多いので、「完治」させるのは非常に難しい場合が多いようです。
しかし、見直したい部分はたくさんあります。
まずは、こまめなお部屋の清掃・ダニ対策・フィルターつき空気清浄機を置く・愛犬のベッド・マットなどを常に清潔にするなど、できるだけハウスダストなどのアレルゲンに触れない生活環境をつくることが大切です。
《 皮膚の状態に合わせたシャンプー選び》
アトピーの犬は、皮膚のバリア機能に問題がある場合が多いようです。
皮膚のバリアがうまく機能していないということは、外部から細菌などの病原体や異物が侵入しやすくなるということです。アトピーの犬の皮膚の状態はさまざまで、いろいろな症状が混ざっていることもあるため、愛犬に使用するシャンプー類やシャンプーの頻度等は、皮膚の状態にあわせて使用することが大切です。
犬のシャンプーは合成界面活性剤を使用しているものがとても多く、それが原因で皮膚トラブルをおこしている可能性もあります。またシャンプーのすすぎ残しのないように気をつけることと、皮膚の保湿も大切です。直接皮膚にあたるものや洋服にも気をくばりましょう。
《 免疫反応を抑える 》
本来免疫とは、外部から侵入しようとする病原体や異物を攻撃して排除して体内環境を守ろうとする機能のことです。しかし、アトピーの場合は、その免疫反応が異常に強すぎるために、自分の体を傷つけるほどの強いかゆみや炎症をおこしてしまいます。
そこでこの免疫反応をおさえる薬を使って治療する代表的な治療というと、ステロイド剤や免疫抑制剤などがあげられます。しかし、これらの薬剤は副作用の問題が指摘されており、いいことばかりではないようです。
近年、副作用のすくない治療としてインターフェロンガンマ療法や減感作(げんかんさ)療法などという治療が注目されています。
信頼できる動物病院でよく相談しながら根気よくケアしてあげましょう。
犬のノミアレルギー
ノミに刺される事によってノミの唾液が体の中に入り、これがアレルゲンとなって発症します。
強いかゆみが生じるため、何度も引っかいてしまい、化膿性の皮膚炎を起こしたりすることもあります。
ノミの数には関係なく、1匹いただけでも発症する子もいます。
背中や腰の毛が抜け、赤い発疹が見られます。肛門の周りや耳の後ろに見られることもあります。
犬の接触性アレルギー
犬が触れるもの、生活環境のあらゆる物質がアレルゲンとなり、発症します。
とくにノミ取り首輪やフローリングワックスなどの薬品や薬物が含まれている物質などで症状がでる犬が多いようです。
症状としては、そのアレルゲンが接触した部分の痒みや脱毛が見られます。
症状がどこにでるかチェックしましょう。
《 アレルゲンの特定 》
アレルゲンとしては首輪、洋服、食器、敷物など、愛犬に直接触れるものすべて考えられます。
それらを洗うときに使う人間用の合成洗剤が原因の場合も考えられます。
そのほか、家の中で飼っている場合、フローリングワックスの可能性もあります。
どこに症状が部位をよくチェックして、可能性のあるアレルゲンと接触しないようにします。
アレルゲンを特定し除去するか、別の素材へ替えたりすることにより、治癒することが多いです。
可能性のあるもの、周りをよく観察してできることから対処してあげましょう。
犬の食物アレルギー
食物アレルギーはフードに含まれる。
アレルゲンとなる、牛肉、豚肉、鶏肉、魚、卵、大豆などのタンパク質、ミルクなどの乳製品、とうもろこし、小麦などの炭水化物などが原因で発症し、主に全身の皮膚の痒み・下痢などの症状がでます。また痒みの症状が耳にでることが多いようです。
外耳炎が繰り返される場合、食物アレルギーを疑い、食事療養を検討することも多いようです。また、ペットフードに含まれる合成添加物(着色料・保存料など)も原因の大きな一つとなっています。
ペットフードの高い安いや、ブランドには関係がありません。
《 アレルゲンを特定 》
とにかくアレルゲンを特定しそれを外すことで、今、与えているペットフードを見直すことが一番大切です。しかし、ペットフードを変えたからすぐ治る・改善が見られるというものではありません。
犬の血液が入れかわるのに2~3ヶ月かかるからです。
また、食物アレルゲンを特定することは容易ではありません。
信頼できる療法として低アレルギーの食事療法がありますが、この療法はアレルギーをおこす食物には犬の個体差・体質などによりかなり差がありますし、2~5週間ごとに食事の種類を変えて調べていきますので、長期戦の心構えが必要です。
次におすすめするのが、毎日の愛犬の食事を手づくりにすることです。愛犬にどんな食べ物を与えているのか、飼い主さん自身がとてもわかりやすいからです。
無添加飼育されたお肉、自然栽培・有機栽培された野菜でアレルギーに起こしにくい素材を使い、愛犬の年齢・体型・性格・体調を考えて毎日メニューを変えてあげることができます。
愛情のこもった手作りごはんです、愛犬もきっと喜ぶでしょう。
《 アレルギーをおこしにくいとされる食べ物 》
肉 鶏、七面鳥、ラム、カンガルー、鴨、馬
魚 白身の魚、サーモン
穀類 オートミール、玄米
野菜 じゃがいも、トマト、にんじん、ブロッコリー、セロリ、パセリ
果物 リンゴ、アボカド
海草 コンブ
油 EXバージンオイル、グレープシードオイル、キャノーラオイル
犬の熱中症と応急処置
熱中症…暑い夏はとくに人も犬も気をつけなければなりません。お天気の良い日に車中に長時間愛犬を放置していませんか?すぐにもどるから…なんて安易な考えは危険です。
熱中症は人間にだけでなく犬にとっても大変危険で、死に至ることもあります。
犬は人間と違い汗をさほどかきません。
肉球にしか汗腺がないので、舌をだして「ハアハア」と激しく呼吸すること(パンティング)で、唾液を蒸発させて体の熱を外へだすしかありません。
そして、たくさんの毛に覆われていますので、人間より暑さによわいのです。だからといって、犬の毛をサマーカットにするのもおすすめできません。
人間から見ると毛が暑苦しそうにも見えますが、あのふわふわの毛の中に空気を溜め込み体温調節をしているので毛をあまり短く切るのはやめましょう。
一度カットするとホルモンバランスでフルコートにならなくなってしまうワンちゃんの種類もあります。
熱中症にならないように心がけるとともに、もしそうなった場合の応急処置法を
頭に入れておいてほしいと思います
《 犬の熱中症の症状と応急処置 》
熱中症とは、夏などの暑い環境下で起こりやすく措置が遅れると脳障害を起こし、結果死に至ることもある恐ろしい病気です。
犬の体温調節は主に口を開けて舌をだして水分を蒸発させて体温を下げたりしますが、気温が高い時・湿度がたかい梅雨時期・換気のわるい場所や直射日光下に長時間置かれるとこの体温調節が間に合わず、体温が上がったままなかなか下がらずに高熱・脱水といった熱中症の症状が現れます。
症状のチェックポイント
・激しい呼吸、あえぐような息(初期症状)
・大量のよだれ(初期症状)
・足元がふらつく
・グッタリして元気がない
・意識がなくなる
対策・処置
初期症状が見られたらとにかく急いで体を冷やしてあげることです。
同時にかかりつけの動物病院に連絡し、できるだけ早く連れて行きましょう。
携帯電話などにあらかじめ動物病院の連絡先を入れておくと便利です。
すぐに動物病院へ連れて行けない場合は、応急処置をしながら安静にさせます。
症状が落ち着いても安心せず必ず動物病院へ連れて行きましょう。
応急処置
・直射日光のあたらない涼しい日陰へ移動させる。
・体温を下げるために、水をかけたりぬらしたタオルを体にかけてあげたりします。
冷やす場所は、犬の後頭部と肺・足先を中心にゆっくりとシャワーなどで水をかけて体を冷やしていきます。
濡れタオルや保冷剤・氷まくらなどがあればそれを使います。
一度熱中症になるとなかなか体温が下がらないので、冷やしすぎを心配する前に、しっかり体温を下げることを考えましょう。
そのときの環境にもよりますが、抱きかかえられる小型犬なら浴槽などで水に頭以外の体ごと浸してあげます。
犬の平均体温は37.5~39.0度が正常ですが、体温が41度で脳に障害が起こる可能性があり、体温が43度になると死に至る確率が高くなります。
症状が見られた時は、急いで体温を下げるように努めできるだけ早く動物病院へ連れて行きましょう。
《 犬の熱中症予防と環境づくり 》
熱中症になりやすい場面をしっかり頭に入れて熱中症の予防、環境づくりに気をつけましょう。
● 車の中
「日陰だから」「曇り空だから」「ちょっとの間だけだから」「窓を少しあけておくから」なんて車内でお留守番をさせることは絶対やめましょう。
真夏の車内は、あっというまに60℃以上にまで温度が上昇してしまいます。
わずか10分…その10分でも命に危険があるということを忘れてはいけません。
● 部屋の中
部屋の中でも、風通し悪いなど換気が悪かったり、室温が高くなると熱中症の危険があります。
防犯上、窓を閉め切ってでかけるのが通常です。
愛犬ひとりでお留守番をさせる時には、部屋の温度管理や愛犬の状態をチェックすることができないので、エアコンをうまく利用することをおすすめします。
閉めきった室内での扇風機は、汗をかかない犬にとって涼しいとは感じられませんし、体を冷やす効果はほとんどないです。
エアコンの設定温度には注意して、部屋が冷えすぎないようにしてあげましょう。
● お散歩中・お散歩後
日中のお散歩は絶対にやめましょう。日中のアスファルトに触れたことがありますか?
日中のアスファルトは熱く焼けていて、非常に高温になっています。
愛犬は地面に近い所を歩くので、地面の熱の影響をうけやすく、裸足で歩いているのと同じなので、やけどの原因にもなります。
夕方ののお散歩もアルファルトに熱が残っていることがあるので注意し、水分はこまめに補給しながら長距離の散歩コースは避けるようにしましょう。
高齢犬など、愛犬の体調をよく観察して無理に散歩に行かないようにしましょう。
● 屋外の犬舎・係留
直射日光のあたるような場所に、犬をつないでおくことは絶対にやめましょう。
風通しがよい日陰に犬舎を移動する、もしくは日よけを使って日陰をつくってあげる、いつでも日陰にはいれるようにしておくことが大切です。水をまいてあげるのもよいです。
コンクリートの上は熱がこもりやすいし、時間の経過により日陰の位置も変わります。新鮮な飲み水を欠かさないように。
● 極端な「サマーカット」は避けましょう
夏場はとくに、被毛が立派だと見た目に暑苦しく感じることも多いですが、「涼しそうだから」などといった理由で、犬の毛をサマーカットにするとそれが熱中症の原因になることも多いのです。
犬の被毛には、太陽の熱を直接皮膚にあたらないように防ぐ働きがあります。
その被毛を極端に短くカットしてしまうと、太陽の熱が直接あたり、体温は上昇しやすい状態になってしまいます。
強い紫外線が皮膚に直接あたるのも、皮膚によくないのは人も愛犬も同じです。
夏バテとは?
夏バテとは、数日から数週間にわたる食欲不振・倦怠感・脱水症状が主な症状のことをいいます。
これに似たもので、熱中症というものもありますが、熱中症は、短時間に起こり、体温の上昇や極度の脱水のため、早急に対処しなければ命に関わるものなので見極めが大切です。
夏バテの症状
《 犬の夏バテこんな症状こんな症状に要注意 》
■食欲がない
人間と同じで夏バテのサインです。
■動きたがらない
大好きなお散歩に行きたがらないなどは要注意。
お散歩の途中で動きたがらないのも要注意。
■呼んでも反応が鈍い
いつもならすぐ反応するのに…そんな時も要注意。
■首の皮を引っ張っても元に戻るのが遅い
水分が不足している証拠です。脱水状態が続くと、ワンちゃんの血液はドロドロになり、
尿路結石などの病気となる危険性が高まります。
■だるそうに見える
暑くて弱っているのかもしれません。ワンちゃんにとって暑さは大敵。
だるそうにしているのは、注意信号です。見逃さないように。
《 夏バテしやすい犬種など 》
■ハスキーやボルゾイetc
北方出身の犬は特に暑さに弱いといわれています。
■シーズーやブルドッグetc
短頭種(鼻の頭が短い)・短毛種は犬は夏バテしやすい。(※1)
■高齢
抵抗力や生理機能が低下しているので、環境の変化や体温調節がうまくできない。
■肥満
脂肪の層が保温材となって、体温がさらに下がりにくくなります。
■心臓に持病
暑いと心臓に負担がかかり、悪化する可能性があります。
■寒い地方から移動してきたばかり
気温差が激しいと、温度の落差にすぐ対応できないため夏バテになりやすい。
(※1)短頭(鼻の頭が短い)犬種は、本来は長い鼻の部分に収まるはずの器官がすべて潰れたお顔に収まっているために、軟口蓋過長症という疾患になりやすいです。(喉ちんこが長過ぎて呼吸しにくい) イビキがひどい犬なんかはこの症状です。
また鼻腔狭窄といって鼻の穴が狭すぎたり、器官が弱かったりと品種改良による弊害が多いです。
呼吸がしにくいために、夏場は呼吸困難に陥りやすく、体温調節のためのパンティング(ハァハァいって呼吸する方法)もガーガーいってしまいとても辛そうにします。
雪国出身の犬も夏には弱いようですが、短頭(鼻の頭が短い)犬種の方がはるかに夏の暑さには弱く、
とても気を使う必要があります。
《 夏バテ予防法 》
■散歩
朝なら、路面の温度が上がらない早い時間帯が好ましい。(※2)
夜なら、十分に温度が下がってから。
まめに日陰に入ったり、水分補給もしましょう。
■留守番
クーラーを適温に設定する。
犬の体温は人間より1~2度高いので、それを目安に。
飲み水もちゃんと置いておきましょう。
■食事
水分が不足しがちであれば、水分を多く含んだウェットフードもオススメです。
おからもおススメです。
おからもダイエットが必要な犬にもいい食材ですが被毛の状態も良くなる(毛艶がよくなる)という効果もありとか。
お腹で水気を含むとかなり膨張するので食べさせる量が少量でも便の量は増えます。
※ 注意 ※
大豆アレルギーの犬もいるので大豆系の食品を食べたことが無い犬に与えるときは、まず少量与えて便や皮膚に異常が現れないかチェックして下さい。
あとは飲み水にごく少量の緑茶を混ぜるのもGOOD!
■お出かけ
短時間でも犬を車内放置はしないようにしましょう。
犬によっては、あまり野外で遊びまわると熱中症になる場合もあるので、温度などに注意!
■寝るとき
冷却マットなど、横になって体を冷やせるものを用意。
(※2)
アスファルトが太陽光により熱くなり、犬のパッド(肉球)が火傷するので。
(真夏のアスファルトの温度は、50~60度にもなるそうです。)
放置しておくと、傷口から細菌が入り込み化膿し大事になりかねません。
良く昼に散歩している方を見かけますが、虐待行為をしているようにしか見えないのでやめましょう。
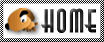
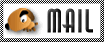
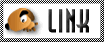


 質問は・・・
質問は・・・